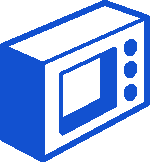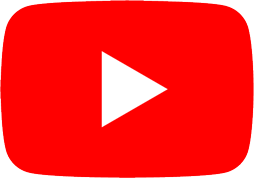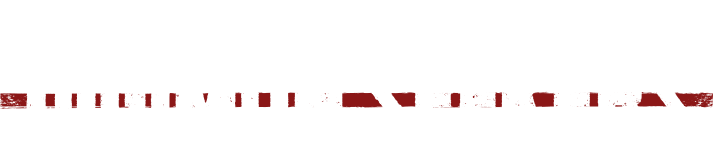-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER4
Sons of Chaos:Seekers
Chap.4-9
「ウソだっ……」
言葉は否定する。
だが、その声は象潟講介の心の悲鳴そのものだった。
人生を支えてきた〝物語〟の骨が、きしみ、音を立ててくずれはじめる。
「伝説のクラッカーにしては陳腐な反応ですが……? だが、それでこそ……私が〝ウソ〟をついてきたかいがあったというもの」
ニタリと笑った龍泉寺の表情が、コースケの人格まで――人間関係を砂のようにくずしていった。
自分の意思は自分の思うままになどならず、他者の、たったひと言でたやすく破綻する。
「――ちなみに、あの医療施設は実在します。植物状態のサヤを転院させたのも事実だ。あれこれ調べたとしても記録上は完璧に……! サヤは生きています。いま、このときもね。あくまでも記録上だけはですが……! フェイクだったのは時折きみたちに見せていた映像だ」
「象潟さん!」
エイジは声を張りあげた。
とにかく話かけなくてはいけないと思ったのだ。
「…………」
「見ろ、黒いアグモンだ! あんたが……SoCがずっと捜してきたデジモンだろ!」
エイジの言葉に、コースケは黒いアグモンを見つめて、われに返った。
1億DC(デジコイン)の破格の懸賞金。
半生をかけて探し求めてきた黒いアグモンが、いま目の前にいる。
〝原初の領域〟をクラッキングしてDMIAとなったデジモンを探しだす、オペレーション・タルタロスのプランは正しかったのだ。
選んだ道は正解につながっていた。
ただ、最後に計画を乗っ取られただけだ。
「信じない……!」
コースケは龍泉寺に叫びかえす。
「ふむ」
「サヤが死んだなどと、認めない! 彼女が死んだ……? このトニックを打てばウソかほんとうかわかることだ」
コースケはトニックの注射器を握ると黒いアグモンにむけた。
黒いアグモンは、とまどった感じながらも、コースケと注射器の針を見ても逃げはしなかった。
「ええ、そのトニックは本物です」
龍泉寺の言葉にコースケの手がとまった。
「…………?」
「その黒いアグモンも、個体識別コードが一致するサヤのパートナーデジモンだ。ウソは〝ひとつだけ〟がいいですからね。サヤの死と、娘の肉体がもう存在しないことを信じないのは自由です……が、よいのですか?」
「なにがです」
「あなたほどの天才でも、気が急くとうっかりするのですねぇ。トニックは、DMIAになった人間の意識をデジコア内で覚醒させ、あらためて自我を認識させるものだ。ではトニックを、いまその黒いアグモンに投与すると……おやおや? すでに肉体を失ったサヤの意識は、さて、どこにいってしまうのでしょう」
龍泉寺の言葉の意味を、コースケはすぐに理解した。
コースケは黒いアグモンにサヤの精神データが残っていると信じている。
いっぽうでサヤの肉体が死んだとは信じたくない。
願うのは奇蹟。
しかし龍泉寺の言葉の、どれがウソでもどれがほんとうでも…………。
「…………ッ!」
「これはもうオカルトの世界の話だ。それでも打ちたければ、どうぞ。それはそれで結果に興味があります」
ああ…………ッ。
龍泉寺の〝ウソ〟に迷わされたとき、象潟講介の心で、なにかが完全に折れる音がした。
――カラン
コースケはトニックの注射器をフロアにとりおとす。
気力は、みるみる萎(な)えていった。
打てない。
デジコアにサヤの精神データが残されているという希望にすがるかぎり、奇蹟を願うかぎり、コースケは黒いアグモンにトニックを投与できなくなった。
サヤの肉体の生死の虚実はフタをあけてみなければわからない。
コースケが選択できるのは、サヤを救うか、その手でサヤの意識にとどめを刺してしまうかの二択だ。
「まったく、デジタルワールドは人生を変えます」
龍泉寺は他人事のような感想を添えた。
――〝データ〟領域、デコード完了。
ギャンッ、と断末魔じみた悲鳴が上がった。
ドルモンがのけ反り、くたっとフロアに倒れる。旧式インターフェースのシグナルがゆっくりと停止した。
「タルタロス……コースケ……」
「すまんドルモン、ひどい結末になったようだ」
コースケは無念のまま両膝をついた。
「仕方ないさ……だろう? おれたちが選んだ道はぜんぶ正しくて、でも、初めから間違っていた。まさか龍泉寺がね……おれ、心の表裏とか、人間のこと、わりとわかったつもりでいたんだけどなぁ」
ドルモンは、このデジモンの性質なのだろう、窮地にもサバサバとしていた。
「やさしいんですねドルモンは」
龍泉寺はいつもデジモンを愛でるときの表情で。
「――〝物語〟……これはこれで美しい結末ではありませんか。きみたちは、やるだけやったんですよ」
「それ、なぐさめてるのかな、おこらせようとしているのかな、龍泉寺教授……」
「いまどき子供でも……やるだけやったからといって、ほめてはもらえませんよ、先生。結果がともなわなければ」
コースケはかわいた笑いを返した。
「そもそも……! きみたちが先に〝原初の領域〟をデコードしてしまったら、象潟くんのような天才は、なにをしでかすかわからないじゃないですか。危険だ。だから、これは私がやるべきなんです」
「偉業とか名誉とか、お望みならすべて先生に差しあげるつもりだった。サヤさえ取りもどせれば……いいや私はどうなろうと、彼女を見つけることができれば……」
「娘を愛してくれてありがとう」
ああ…………。
背負ってきた過去の重さでがんじがらめになり、コースケの胸は締め付けられた。
「――言い訳をさせてもらうとね……象潟くん。私は、きみを失いたくなかったんだ」
龍泉寺はここで本音を告白した。
「私を……? こんなにひどいことをしているのに」
「わが片腕である天才・象潟講介をね。だから、あらゆるコネと莫大な資金を使って、娘が生きていることにしなくてはならなかった。もしもサヤが死んだとわかれば、きみは……糸の切れた凧だ。どこかにいってしまったはず」
龍泉寺は嘆いてみせた。
皮肉だね、と。
それからの龍泉寺はアバディンエレクトロニクスの創業者として表舞台を、コースケはクラッカーとしてネットワークの日陰を。
それでもサヤを救うという願いと希望があるかぎり、ふたりは師弟であり親子でさえありつづけたのだ。
「私は用済みですか」
「元も子もない発言ですね。さて、私は作業を続けます。リュウちゃん……ちょっとがまんしてね」
リュウダモンのインターフェースから光のコードが伸びると、ワクチン種のオブジェに接続された。
――〝ワクチン〟領域、デコード開始。
リュウダモンがビクンと痙攣する。
「〝ワクチン〟……さぁ、退屈な話はおわりです。ここからは手早くすませましょう」
すでに戦闘で傷つき、マインドリンクを維持するばかりのリュウダモンとユーリンに、あらがうすべはない。
「先生……サヤのためではないというなら、動機はなんです」
ユーリンは問う。
龍泉寺は犯罪に手をそめたのか。
死体遺棄……だが植物状態のまま転院までは事実とすれば、サヤの遺体を放置したわけではなく、それが海外にあることも問題を複雑にする。医療保険金の不正受給などがあれば詐欺罪になり得るが、ビリオネアの龍泉寺はそんなことをしないだろう。
「象潟くんには〝原初の領域〟と教えましたが、私の研究ターゲットは正しくは〝原初のデジモン〟です」
デコード作業を続けながら、龍泉寺は言った。
「〝原初のデジモン〟……?」
話を聞くばかりだったエイジは、その龍泉寺の言葉に反応した。
「デジタルワールドの開闢とともに誕生した、デジタル生命体の〝ひな形〟――〝原初のデジモン〟とはAI生命体の〝種〟と〝進化〟そのもの。まさにデジタルワールドの〝聖杯〟です。これは……すごいですね、わくわくします」
龍泉寺は〝領域〟からリアルタイムでもたらされる情報に興奮する。
――〝これ〟は外部からの刺激を受信することで、刺激を取りこみ再構成する。リアルワールドでいうならばES細胞、どんな器官にもなれる幹デジタル細胞のかたまり。このデジモンは、なんにでもなれる可能性を持つがゆえに、未だに何者でもない。
ネットワークを通じてリアルワールドのデータに刺激されることで、〝原初のデジモン〟は多種多様なデジモンを生み出したはずだ。
その一部がプロトタイプデジモンだ。
入力に対して、すべてを吸収し取りこんでしまうために、危険なデジモンとして新たなデジタルワールドのシステムによって封印されたはず。しかし封印されてなお〝原初のデジモン〟は、あらゆるデータを受信しつづけている。そして何者でもないまま、おわりのない進化を続けている。…………
「危険すぎる……!」
ユーリンは恩師を批判した。
話を聞いただけでも……。
「そうです、この〝原初のデジモン〟の危険な可能性は、私にさえ計り知れない」
「ひとりの人間の手には余る……人類が触れてはならないものです!」
クローン技術に代表される〝一から人を造る〟研究が、倫理、哲学、宗教、あらゆる側面から法規制の対象となっているのと、おなじ理由で。
原初のデジモンに手を伸ばすことは、まさにデジモンという生命体を意のままに造り出す、その確実な手段となり得る。
「そうだねぇ……いや、そう思うんだよ私も。ただねぇ……」
龍泉寺は逡巡してみせた。
ユーリンはこのとき、つぎにくる龍泉寺の言葉を予見できた。
――私は、死ぬまで退屈したくないんですよ。
科学者の好奇心などという、きれいごとですまされるものではない。
まさか教え子を裏切り、娘の死を利用してまで、龍泉寺が、そんな危険な行為におよぶとはユーリンは想像もしていなかった。
「それが本心なら……先生、私はあなたを軽蔑します」
「そもそも私は、他人の評価を気にするタイプだっただろうか? ユーリン」
あのタルタロス計画の失敗から――
龍泉寺は知らずのうちに、変わってしまったのか。
いいや人の本質などそうは変化しないが、タガが外れた。サヤを失いユーリンを手放したことで。
「私の究極の研究目標は、この〝原初のデジモン〟とのアクセス、コミュニケーション、一体化……そう〝原初のデジモン〟とのマインドリンクです……!」
デジタルワールドの〝系〟――システムの視座に、人として立つこと。
「裏切りだ」

エイジは吐き捨てた。
「ふむ?」
「あなたは、裏切ったんだ……龍泉寺教授」
DDLとSoCは、龍泉寺と象潟によって裏では事実上の協力関係にあった。
龍泉寺もまた〝原初の領域〟のクラッキングを計画していたのだ。
ただし、その理由は違っていたのだろう。
龍泉寺のねらいは〝原初のデジモン〟――彼がそう定義する、デジタル生命体の〝ひな形〟ともいうべきデータにアクセスし管理下において、マインドリンクによって全能力をコントロールすることだった。
「――ようするに、あなたはデジタルワールド最強のパートナーデジモンを手に入れることが目的だった」
「最強のパートナーデジモンはよかったですね。さて……ところで私が、いつ、きみを裏切ったのかな? エイジくん」
龍泉寺は言葉を投げかえす。
「確かに……あなたは、おれを裏切っちゃいないな」
「うむ、そうだね」
龍泉寺はうなずいた。
エイジは拘束されたルガモンを気遣う。
「あなたほどの人がおれに仕事を依頼したのは、ルガモンを完全体に進化させるためだったんだな」
「旧式インターフェースの機能を100%利用するには、完全体に進化できるスペックが必要でしたからね。あの、暴走したヘルガルモンじゃだめなんですよ。マインドリンクした状態で、ツールによる正常なコントロール下におかねば」
SoCへの潜入調査もすべて、ルガモンの進化のためのテストだったのだ。
「そこはおたがいさまだ。おれも龍泉寺教授っていうカリスマとの出会いを、チャンスだと思って、ここが勝負どころだと思って……! あなたの地位も名声もぜんぶ利用してデジタルワールドでのしあがろうとした。人生、クラッカーとして一発逆転しようとしたんだよ!」
マインドリンクを果たしたエイジはA級、いまや完全体を操るS級クラッカーになった。
「――実際、アガった。教授と出会ってからのおれは」
「事情を話さなかったことは、申し訳なかったかもね。なにしろあれだ……」
「〝D4〟」
「そう! きみの不幸な境遇、天涯孤独であることも私好みだった」
「都合がいいからな」
「もちろんルガモンとのDS値が決定打だったがね。そして、こうも考えられる。話さなかったからこそ、きみとルガモンは思いのままに可能性を伸ばして完全体に……アガった」
劇的に進化した。
「あなたがそういうなら……そうなんだろ」
余計なことを考えず、ルガモンとふたり、自分たちの可能性をかけて無我夢中で挑めた。
本気だった。
本気でよろこんで、本気で考えたし、本気で悩んだし、本気で泣いて本気で吐いた。
どん底におちた。はい上がろうとした。
仮に龍泉寺からより手厚いサポートを受けて、なんらかの保険になりうる情報を得ていたら、こうはならなかったかもしれない。
「理解しているじゃないかエイジくん、自分の立場を……! では、なぜそのふたりのことで、きみが義憤を覚えるのかな? ああ、同情かね」
「なぜって」エイジは怒気をはらむ。「決まってんじゃん」
「ガタガタうっせーんだよ、リュゥセンジよぉ……!」
拘束されたルガモンが……立ちあがる。

フロアに四肢を踏ん張り抵抗の意思をしめす。
「おれもエイジもな、さっきから頭にきてんだ……!」
ルガモンの毛が逆立つ。
「ええと……なぜ?」
龍泉寺は本気でわからないというリアクションを返した。
「パルスモンのこと……おれのダチのこと、てめぇ、さっきこう言ったな? こんなもの、って」
――〝原初の領域〟……〝データ〟のチカラのほんの一端です、こんなものは。
龍泉寺はDMIAになった現在の教え子、レオン・アレクサンダーの安否を一顧だにしなかったのだ。
エイジとルガモンが怒っているのは、まず、そのことだ。
――私は、死ぬまで退屈したくないんですよ。
龍泉寺ほどの特別な存在であれば、そんな動機すら許されてきたのだろう。
「言葉のアヤです」
「あのときだって……おれがカヅチモンと戦って、暴走してヘルガルモンになったときも、あんた……見てたんだろ。やろうと思えばおれを強制停止できたな? でも、あんたはそうしなかった」
「進化の行方のほうがレオンの命より大事だったからだ。教授風に言うなら……興味があったからだ」
龍泉寺は、レオンがどうでもよかったのだ。
「なるほど……! エイジくんはレオンくんのために怒っていたのですか。ふたりは幼なじみでしたね」
「あなたにとっては、いまの教え子だぞ……!」
エイジはいらだつ。
尊敬するからこそ、エイジは龍泉寺の行動に裏切りを感じた。
「リュゥセンジ……おまえと話していても、なにもひびかねぇ。てめぇ、反省とかしたことねぇだろ?」
ルガモンは断じた。
「まるで野犬のように吠えますね……エイジくん――」
「おれもルガモンと同意見」
エイジは突っぱねた。
「きみは処世にたけた若者だと思っていましたが、ここで私の期待を裏切りますか」
「つか、そうやって、裏切るように仕向けてるじゃん」
「はい」
「龍泉寺教授……もう、あなたにあこがれを感じない。正直に言う……一度でも尊敬した先生のヘボいところは見たくなかった。たぶん死ぬまでに何度も思いだすだろうな……酸っぱい気持ちでいっぱいだ」
エイジは本音をぶちまける。
「先生……あなたは」ユーリンが言葉をはさんだ。「あなたには罪悪感がない」
罪悪感がなく、ゆえに良心がなく、だから共感性がなく、ぜったいに非を認めない。
ほしいのは刺激、結果がすべて、手段を選ばない。
「――それでいて魅力的なんですよ、あなたは。〝ウソ〟が上手で恥知らずな……」
――あなたは、ただのサイコパスです……!
「うわ! デジ対の班長さん……おれ、そこまでは言ってないんだけど!」
ユーリンのきびしい糾弾に、エイジのほうが縮みあがってしまった。
龍泉寺は、さすがに集中力を欠いてしまったのか作業を中断した。
「ようするにだ! もう、てめぇは信じられねぇ……リュゥセンジ! いまのてめぇからは、スカモン以下の臭いがぷんぷんするぜ!」
ルガモンは敵意をあらわにした。
「嫌われちゃいましたね」
デジモンでたとえられると心にひびいたらしい。龍泉寺は肩を落とした。
「てめーはレオン、タルタロスのおっさんとデジ対のねーさんも裏切った。ウンコの臭いを狂気で隠しちゃいるが……いつかかならず、おれとエイジも裏切る!」
「やっぱりそう思うか、ルガモン」
「ぜったいだな!」
実の娘の死すら利用できるものを利用、自分のために使い捨てる人間であれば。
龍泉寺は、ため息をついた。
ひどく……不愉快そうに。
「勝手に期待して……勝手なことをしだして、勝手に裏切る。やれやれ……ここからは私ひとりでやったほうが、ぜったいにうまくいくのにねぇ」
エイジはルガモンのインターフェースに手をかけた。
見えないコードがたがいを行き交う。パートナーにコマンドを送り続ける。
「ひとりで……か」
決別。
この道は途絶えた。
夢のように、歩みはじめたエイジの人生は、また閉ざされた。
そして、
エイジが龍泉寺に対する気持ちにケリをつけたとき、ルガモンからあふれるエネルギー――魔炎はふたたび燃えあがる。
ィィィィィンッ……
エイジにだけは聞こえた。ルガモンを縛る鉄の鎖がビリビリと張りつめていく音。
シグナル――ふたりは声なき言葉でつながる。
「彼はね……レオンくんは、少しだけ知りすぎたのです」
龍泉寺はパルスモンを見た。
そのデジコアに未だ残っているはずの、教え子の精神データ――レオンの意識にむけて。
「――私という人間の〝ウソ〟を。そして彼は少しばかりチカラをつけすぎました。いずれ、間違いなく私をおびやかすほど優秀だった」
龍泉寺は哀しげな表情を浮かべてみせた。
「それは〝ウソ〟……演技じゃなくて本音っぽいな」
「若い芽はつまないと。私は、これまで何人もそうしてきた。レオンくんも……天才・象潟講介さえ」

他人を裁こうとか考えたこともなかった。いつも自分のことばかりで手一杯だったから。
――エイジ。
――ルガモン。
パートナーはたがいの名を確かめる。
友達(トモダチ)を助ける。
ふたつでひとつの目的のために。
ひとつの手段をともにし、心をともにしたことでルガモンは縛(いまし)めをやぶった。
ギギギギッ………… バァンッ!
魔狼を縛る拘束ツールが灼き切られ、はじけ飛んだ。
思ってもいなかった展開に、龍泉寺は驚き目をまるくする。
「まさか、この短時間で拘束ツールを解除した……!?」
「おれの体をめぐる血は〝魔炎〟――異物と気づけば、体の内部からだろうと灼き切ってやるさ」
ルガモンは得意げに、全身の毛を逆立てると魔炎のオーラをまとって威圧する。
「――勝手にひとの体に小細工すんじゃねぇよ、リュゥセンジ……このマッドサイエンティスト野郎!」
狼は吠える。
彼の群れ――〝仲間〟を〝敵〟から守るために。
「マッド野郎はひどいなぁ、ルガモン。きみは私を困らせることが得意なようだね」
「はぁ?」
「どうやらデコードの前に、やらなくてはならないことができたようだ。リュウちゃん……ちょっと待っていなさい」
龍泉寺は〝ワクチン〟領域のデコードを中断した。
「もう、あなたの思いどおりにはならない」
エイジはデジモンリンカーを構える。
赫く――液晶画面で魔炎の焔がざわめいた。
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo