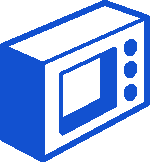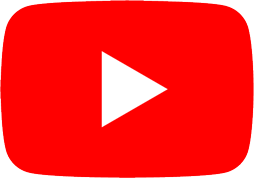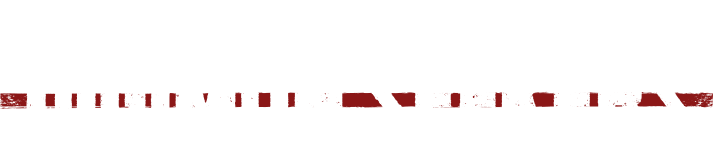-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER4
Sons of Chaos:Seekers
Chap.4-8
すべての情報が遮断された。
体感では一瞬――ほどなくエイジの視界は回復する。
ストーンサークルが逆さまにひっくりかえっていた。
「…………!? え、あれ?」
いいや、フロアであおむけにひっくりかえっていたのはエイジ自身だ。
「ぐっ……」
「ルガモン? どうした!」
エイジは体を起こした。
ルガモンがフロアにつっ伏したまま、苦しんでいる。
「体が動かねぇ……」
どうしたことか――
リュウダモンはもとより、ルガモンとドルモンまでがストーンサークル内に倒れていた。
ホロライズしたコースケとユーリンも。
その場にいた全員が、さっきのシャットダウンの一瞬、気を失ってしまったらしい。
3体のプロトタイプデジモンの旧式インターフェースが光を失っていく。
「…………!」
「ルガモン!?」
ふっ、とブラックアウト。
すぐに再起動――そうしてインターフェースから、今度は正体不明のコードが実行されはじめた。
「なぜ……?」
コースケの声はわずかに震えていた。
仮想モニタのツールが再起動できないでいた。画面はエラーを吐きだすばかりだ。
まったく無警戒のタイミングで、予期せぬかたちで〝原初のデータ〟のデコード作業が中断された。
――おはよう、諸君。
おつかれさまの慰労の言葉を。
エイジはびっくりして振りかえった。
立っていたのは――
「龍泉寺……教授……?」
ふらりと〝原初の領域〟に現れてみせた龍泉寺は、教え子たちに背をむけたまま、言ったのだ。
――あとは私がやりますから。

DDLのラボにいるときの、いつもの服装で。
「先生……?」
「なにを……なぜ……」
ユーリンとコースケも、予期せぬ相手との遭遇にとまどうばかりで。
「ふむ……驚くことはありませんよ」
あの独特の口調で告げると、振りかえる。龍泉寺智則だ。
コースケとユーリンは無言で立ちあがった。
緊張しているのだ。恩師と教え子とは――言葉というコードだけで人の意識を縛ることができる関係だった。
「――そもそもプロトタイプデジモンは、3体とも私が、きみたちに〝預けたもの〟でしたね」
エイジのルガモンはもちろん、ユーリンのリュウダモンとコースケのドルモンもまた、それぞれの人生の節目に龍泉寺が教え子に託したデジモンだったと。
「…………!」
「いつでもできたんです。そして、いまがそのときだ」
――〝拘束(TIE)〟
「ぐっ!?」
「なんだこりゃ……ぐぉっ!」
ドルモンとルガモンがうめく。
リュウダモンにはめた枷と同様のツールが、彼らのボディを縛った。
「拘束ツールだと……? いったいどうやって……」
ドルモンが困惑したのも無理はなかった。
デジモンは通常、自身のセキュリティで保護されている。ツールで捕獲しようとしても、簡単ではないのだ。リュウダモンのときは戦闘で気絶させ、ほぼ無防備だったから容易に拘束できた。
「――言ったでしょう。プロトタイプは、きみたちに預けただけだと」
龍泉寺はこう言っていた。
いまでも、ルガモン、ドルモン、リュウダモンは私のものだと。
「初めから、おれの体に仕こまれていた……!」
「!?」
ルガモンの気づきに、ドルモンがはっとする。
可能性はひとつだ。
拘束ツールは、はじめから彼らプロトタイプデジモンの内部に仕こまれていた。
「リュウダモンに細工をしたんですか……! 先生!」
ユーリンは龍泉寺をただした。
「研究用ツールです。デジモン自体と、みなさんのデジモンリンカーにも……ふむ? 当然、お伝えしましたよね?」
龍泉寺は言ってのけた。
デジモンだけでなく、デジモンリンカーにも一種のスパイウェアが仕こまれていると。
「…………!」
エイジは自分の腕を見た。
デジモンリンカーは24時間エイジをバイタルチェックして、DDLにデータを送信している。もちろんルガモンの育成状態も。
「必要なら、デジモンのコントロールを強制的に奪うことができます。たとえマインドリンクしていようとです。……研究上、当然のことでしょう? いつかのヘルガルモンみたいに貴重なプロトタイプが暴走したら大変だし……ねぇ、エイジくん」
「!」
「きみたちのデジモンは私のツールの管理下にあります。ここまではよろしいですか」
龍泉寺の〝虚像〟はストーンサークルの中央にすすんだ。
3体のプロトタイプデジモンは拘束されて、身動きがとれない。
「――プロトタイプデジモンは〝原初の領域〟にアクセスするためのインターフェースであり……3本のデジモンリンカーが、リアルワールドとデジタルワールドをつなぐネットワークの中継点として機能している」
ユーリンはこの状況を理解しようとする。
(ノイズ……?)
エイジは気づいた。
龍泉寺の姿に、わずかだが時折ノイズがはしっていた。
エイジ、コースケ、ユーリンが腕につけたデジモンリンカーから投影された光を重ねることで、龍泉寺はホロライズしていた。
〝虚像〟にすぎない。
マインドリンクしながらデジタルワールドで〝実体化〟したエイジたちとは違う、ただの映像だ。
けれどもこの〝原初の領域〟で、いま、すべてをコントロールしているのはオペレーションを主導した象潟講介ではなかった。
龍泉寺智則だ。
身につけた装備、与えられたパートナーも、すべて龍泉寺によって管理されていた。そのことは当然、了解もしていたが。
「もともと、おれはDDLで管理されていた……」
ルガモンは思いだそうとした。
彼の過去の記憶は断片的で失われたままだが、〝九狼城の魔狼〟はウォールスラムでDDLに捕獲されたという。
万一、実験中にデジモンが暴走した場合にそなえて、あらかじめ体内に拘束ツールを組みこまれていた。
さしずめ神話にある、魔狼を縛るために神々が用いた〝グレイプニルの紐〟か。
その事実は〝D4〟であり。
デジ対にも検出できないほど巧妙に、研究用ツールには枷が仕こまれていた。
そもそもユーリンには龍泉寺を疑う理由がない。コースケにとっても龍泉寺は最大の協力者だった。
「ルガモン……」ドルモンが言った。「きみもリュウダモンも、おれも……DDLで管理されていた時期がある。そのときに拘束ツールを仕こまれたか……あるいは新型のデジモンリンカーを配給されたとき、そこから感染したか」
デジモン自身にも気づかせないように。
「人間だってね……手術中、おなかのなかにガーゼや器具を置き忘れられたとしても、案外、気づかないものですよ」
龍泉寺は参考にならないたとえ話をした。
「いったい」コースケはエラーまみれになった仮想モニタをたたくと、恩師を見た。「どういうつもりですか、先生……!」
そのときの彼は、まるで、いち学生に戻ってしまったようだった。
「クラッカー・タルタロス風に言うならば……きみの〝物語〟は私の〝物語〟になりました。そっくりそのまま」
いま、ここにはいない龍泉寺が、ここに至ってすべてを乗っ取った。
〝物語〟をクラッキングした。
3体のプロトタイプデジモンが復号化の鍵であるかぎり、いまや龍泉寺だけが〝原初の領域〟のページをめくることができる。
「まぁ、見ていなさい。ひとつずついきますよ」
龍泉寺は淡々と作業をすすめる。
まずドルモンから――あらためて旧式インターフェースと3相克の〝データ〟のオブジェがコードで接続、シグナルが交錯する。
「なにを……!」
「〝原初の領域〟のデコードに決まってるでしょう、象潟くん。そもそもこれって私の役目だと思いません?」
龍泉寺はコースケを一瞥した。
パートナーを乗っ取られた、ホロライズしているだけの無力な天才を。
「――デジタルワールド研究の第一人者である私、龍泉寺智則こそ、この偉業を成し遂げるのにふさわしい」
――〝データ〟領域、アクセス開始。
龍泉寺の声にかぶってアナウンスがされた。
抑揚のないボイスは……〝原初の領域〟のシステム音声なのか……。
「ルガモン!」
エイジはさっきから、パートナーのコントロールを取りもどそうと仮想モニタをたたいていた。
「まいったぜ、こりゃ」
ルガモンは、なかばあきらめの言葉を吐いた。
意識はあるが自由が利かない。インターフェースとして勝手に体を使われている。
強引に作業をとめようにも、龍泉寺はマインドリンクしているわけではなかった。〝虚像〟を取り押さえることはできない。
そもそも……。
エイジは、おそらくコースケもユーリンもだが、龍泉寺の意図がわかっていない。
「私は……!」コースケは龍泉寺に訴える。「サヤを救うという目的は、あなたとおなじはずだ!」
龍泉寺沙耶を。
「教授! 龍泉寺教授!」
エイジは声を上げた。
でも間がわるすぎて、大人の話に首を突っこんだ子供みたいになってしまう。
「なにかねエイジくん? いま私は忙しい……ああ、完全体のインセンティブの件かな? それなら……」
「じゃね-し!」
「ふむ」
「タルタロス……象潟さんにざっと聞いただけだけど! 象潟さんが捜している黒いアグモンのパートナーがDMIAになった、そのサヤさん……教授の娘さんなんだろ!?」
――〝データ〟領域、デコード進展中。
そこで暫時、シグナルがはげしく点滅して進捗がとどこおった。
「ぐっ……!」
苦しみながらドルモンが立ち上ろうとする。
あらがおうと。しかし、
「あの事故のあと、象潟くんが退学しようと会社を去ろうと、私は、できるかぎりのめんどうをみると約束した。ユーリンくんもだ」
龍泉寺はサヤの事故を隠蔽し、教え子の未来を守った。
「――そうするだけの価値が、きみたちふたりにはあった。それからのきみたちは、人生をかけて自分の価値を高め、いま……こうして私に恩がえしをしてくれている」
人類とデジタルワールドに革命をもたらすだろう、恩師の晴れ舞台をセッティングしてくれた。
「いや……教授! 意味わかんねーし!」
「うん、エイジくんは生まれていないときの話だよ」
かみあわない会話に、エイジは強引に割りこみ続けた。
「だから象潟さんの婚約者を……教授の娘さんを助けるって話でしょ? これ!」
クラッカー・タルタロスこと象潟講介の、これは救済の〝物語〟だったはずだ。
エイジとルガモンは、DMIAになったレオンとパルスモンを助けるために、その話に乗ったのだ。
「――なのに、なんでふたりが仲たがいしてんの? 争う理由なくない?」
結局のところエイジは、ここで龍泉寺とコースケ、どちらを支持すればいいのかすら判断がつかない。
「エイジくん……きみはふしぎな青年だね。なにも見ていないようで、すんなりいいところをつく」
「え……いや、ほめるところ?」
「やはり私は、きみが好きだ。だから教えてあげよう……ぜんぶだ。象潟くんには教えなかったこともエイジくんには教える」
「?」
「私はね……黒いアグモン捜しになど、さほど興味はないんだ」
龍泉寺は黒いアグモンには興味がない。
「……って娘さんのパートナーデジモンでしょ? 興味がない……? だって、そのためにトニックを……象潟さん!?」
人生の罠は、いつも足もとに穴をあけて。
「興味がない……って……」
コースケは知っている。
この教授が「興味がない」ということが、なにを意味するかを。
「言葉どおりです。〝失ったもの〟は、それはそれ。象潟くん……そんなものに半生を費やしてきたきみの計画は、まさに壮大な徒労の叙事詩だったね」
「タルタロス! コースケ……だめだ! 折れるな! 考えろ!」
動けぬドルモンが悲鳴を上げた。
黒いアグモン……DMIAになった娘に興味がない……。
「先生……ッ!」
ユーリンは声をしぼりだす。
「なにかね」
「私は、いつも考えていたことがあります。いいえ……考えないようにしていたことが」
すると龍泉寺は――確かに笑ったのだ。
「その予感は正しいかもしれないね」
ふいに〝原初の領域〟にインデックスが表示されていった。
どこまでも透きとおった〝原初の領域〟を情報の天蓋がおおっていく。
まるで全天球のプラネタリウム。投影された多階層のツリーを、1本の光のラインがたどる。ひどくシンプルな、どこまでも伸びて広がっていくそれは――
「〝データ〟……あまねく情報の樹形図」
龍泉寺の意思は、微細に、はるか奥の奥までデータをたどって。
――サーチ完了。
〝原初〟の声は告げた。
同時に、なにかのデータがデコード、実体化する。
火花。
チリチリと音をたてる稲妻をまとった妖精を思わせるデジモンは――
「パルスモン!」
「なんでパルスモンが、ここに……?」
ルガモンとエイジは状況がのみこめない。
忽然と〝原初の領域〟に現れたパルスモンの表情はうつろだ。
「エイジくん、ルガモン……どうしたのかな? 正真正銘、きみたちが捜しているレオンくんのパルスモンだ」
「!?」
エイジは息をのんだ。
サーチ……探しあてたというのか。〝原初のデータ〟にアクセスすることで。
「〝原初の領域〟……〝データ〟のチカラのほんの一端です、こんなものは」
龍泉寺は語った。
声はたかぶり言葉は優越感で満ちていた。
「…………!?」
「まさか、全デジタルワールドからデータをサーチできると……?」
ユーリンは言葉を失った。
人跡未踏のデジタルワールド〝深層〟を、デジモンの個体識別コードをたよりに検索した。
想像を絶する行為に驚く間もなく、ふたたび全天球のツリーをたどって光が1体のデジモンを探しあてた。
転送――
エイジたちは息をのんだ。
「黒いアグモン……!」

コースケの眼前に実体化したのは1体の恐竜デジモン、アグモンだった。
一見すると黒というよりはモノクロ――昔の映画やテレビの白黒映像のような印象だ。
「ふむ……やはりマインドリンクした人間の肉体が死亡しても、パートナーデジモンが失われるわけではないのですね」
龍泉寺は、新たな知見を得たといったリアクションをする。
「…………。え?」
エイジは龍泉寺の言葉がとっさにのみこめない。
――マインドリンクした人間の肉体が死亡。
「サヤは」ユーリンの心の片隅にあった不吉な予感は的中した。「もう彼女は、この世にいないというんですか!」
龍泉寺の頭上に仮想モニタが展開する。
映ったのは――医療機器のカプセルのなかで、色のついた溶液に浮かんでいる女性の姿だった。
「サヤ……!」
デジ対の班長は目に涙を浮かべた。
映像はノイズとともに消失する。
フェイク。
「そう、サヤは死んだ。とうにね」――――
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo