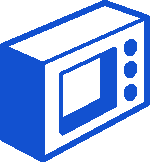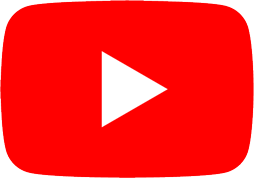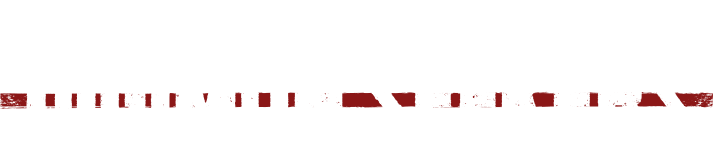-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER4
Sons of Chaos:Seekers
Chap.4-7
〝原初の領域〟に出現したのは、なにかと問われれば答えに困ってしまうオブジェだった。
「な……なんだ、こりゃ?」
ルガモンは腰がひけて、ドキドキしていた。
「おまえが出したんじゃないのか、これ?」
「知らん! あー、びっくりした」
「あはは! ルガモン、おまえでもそんなふうに腰を抜かすんだな!」
エイジはちょっとおかしい。
「おまえはビビらなかったのかよ! エイジ!」
「いや、まぁ……ここデジタルワールドだしな」
エイジは頭をかいた。
奇想天外なウォールスラムの風景を見たあとでは、なにもない空間からなにかが現れたくらいじゃ、もう驚かない。
「あはは、エイジのほうが順応してるね……そう、見えているからといってあるわけじゃないし、見えていないからといってないわけじゃない」
「ドルモン、めんどくせー話はお利口な頭のなかだけにしろ! おれがびっくりしてるのはだなぁ……!」
「…………」
「…………」ルガモンはオブジェをじっと見た。「こいつが、えーと……なんか、あれ、どっかで見たことある気がするな」
「おまえ、それ、いま考えてるだろ」
エイジもオブジェを観察する。
球体のオブジェに刻まれたマークは……。
「3相克の……!」
声をもらしたのはユーリンだった。
「…………あ! DDLのロビーで見た!」
エイジは思い出した。
――デジモン分類学の基礎となる3属性――〝ウィルス種〟〝データ種〟〝ワクチン種〟のモチーフだね。
ルガモンの頭上にマークが刻まれたオブジェが移動した。
「それはウィルス種……つまりルガモン、きみのだ」
説明するドルモン、横たわったリュウダモンの上にも、それぞれの属性マークを刻んだ球体が浮かんだ。
〝ウィルス種〟
〝データ種〟
〝ワクチン種〟
それらは3種のプロトタイプデジモンが〝原初の領域〟を訪れたことに反応し、出現した。
「このオブジェは端末、プロトタイプデジモンはインターフェース……さぁタルタロス、ここが〝聖杯〟の城だ」
「長い物語だったな、ドルモン」
「そうだね。でも、祝杯は計画が成功してからだ」
ドルモンとコースケはうなずきあう。
「ゲートクラックに成功、〝原初の領域〟に到達……! フェイズ3コンプリート。オペレーション・タルタロス、引き続きフェイズ4へ」
コースケは一歩前に出た。
「象潟さん! いよいよ……!」
「これより〝原初のデータ〟へのアクセスを試みる。エイジ……マインドリンクはまだいけるな」
コースケはエイジを見た。
「もちろん!」
エイジはパートナーの背中に手を置いた。ドルモンは尻尾を軽く振った。
「〝原初の領域〟……」
ユーリンほどのハッカーであっても現状認識が追い付かない。
「この場所のことは、きみでも知るまいユーリン。論文になっていないからな。ここは龍泉寺教授……先生のデジタルワールド発見以来の調査と研究、その結実点だ。私は……この視座からサヤを救う!」
〝サヤ〟――
それが象潟の捜している仲間の名前であることは、エイジにもわかった。
黒いアグモンのマインドリンカー。動画で見た、あの医療用カプセルのなかで液体につかった女性だ。
象潟講介と徐月鈴は、世界初のマインドリンク実験とデジタルワールド探索に参加したメンバーだった。その「タルタロス計画」の失敗でDMIAになったサヤを助けたい、という願いだけはともにしているはずだった。
でも、
象潟講介はクラッカーに。
徐月鈴はデジ対、警察に。
探索事故のあと、ふたりはその後の人生において、まったく違う道を選んだ。
武闘派クラックチームSoCの伝説のリーダー、片やデジ対の班長。
選んだのか、選ぶしかなかったのか。
そこまで研ぎ澄まさなくては生きていけないほど、サヤという仲間の喪失を、人生をかけて背負ったのだ。
結果――戦いを制したのは象潟講介とドルモンだった。
(もしかして龍泉寺教授も……?)
エイジは察する。
龍泉寺教授もまたサヤという女性を――ふたりとおなじかつての教え子をDMIAから救いたいと思っているはず。だから龍泉寺は象潟に〝トニック〟を託した。
そもそもエイジをスパイとしてSoCに送りこんだときから、龍泉寺は……ルガモンが完全体に進化することをねらっていたのかもしれない。ゲートクラックのスペックを満たすために。
そして実際、エイジは期待以上のスピードで進化を果たした。
物語はつながる。
とすると象潟が龍泉寺教授のことを「信頼している」と言ったことの意味が、より重みを増して思いだされた。
デジタルワールドをめぐる人類のストーリーのなかで、エイジはひとり遅れてきた当事者だった。
「――そこのクラッカーの彼が言ってたけど」ユーリンはエイジをチラっと見た。「デジタルワールドの古い管理領域……いずれにしても、ここはとんでもないセキュリティの穴ということね」
「理解がはやいね〝三叉路の魔女〟は」
ドルモンはユーリンを賞賛する。
「コースケ、ドルモン……! あなたたちがしようとしていることは……!」
未だにもうろうとしているリュウダモンに片手を置きながら、ユーリンは怒気をはらむ。
――あなたたちはデジタルワールドそのものをクラッキングしようとしている……!
ユーリンは本質をついた。
「そうだ。ロイヤルナイツをかわして、システム管理者を出し抜いて……乗っ取る」
「危険よ!」
ユーリンは彼女の人生にかけて断言する。
「デジタルワールドの〝神〟になるなんて妄想はしないさ。ほんの一瞬、ほんの一部分でいい」
「ここは……危険! 〝原初の領域〟……? こんな場所を人やデジモンの好奇心のオモチャにすれば……!」
「オモチャはひどいな」
ドルモンが茶々を入れた。
「私は本気なだけだよ。サヤを助けるためだ」
コースケは揺るがない。
「だとしても……ここは危険すぎる! 人類とデジタルワールドの関係を、決定的に破壊しかねない! 私たちは……この場所に触れていいほど、デジタルワールドとデジモンを理解しているというの……!?」
ユーリンの言葉が〝原初の領域〟にひびく。
声と言葉だけが、ここでは命というリアリティを想起させた。
初め〝混沌〟があった。
そして〝論理〟が生じた。〝言語〟だ。デジタルワールドの始まりとは、そんなものだったのかもしれない。
そして感情というノイズによって世界は彩られはじめた。
「サヤのためだ」
それが象潟講介の半生を語るすべてだった。
エイジは象潟講介の〝サヤ〟への想い、執着に、ただならない、そう――〝愛情〟をからめた深い執着を嗅ぎつける程度には人に興味があり多感だった。
クラッカー・タルタロスはDMIAになったかつての仲間といった。
だが象潟講介にとって――その〝サヤ〟は特別な存在だったのではないか。
エイジは、そこまでひとりの女性を愛し、愛しつづけたことはなかった。
でも、その人のことを考えるだけで、人生のすべて、意識のすべてをささげたくなる気持ち、なげうちたくなる気持ち……そのくらいはわかるし苦い経験もある。
「たとえサヤを救うためでもよ……!」
「先生の娘を助けるためだ」
センセイノムスメ。
象潟の言葉をのみこむのに、エイジは少しだけ時間がかかった。
「先生の……娘?」
「DMIAになった仲間は龍泉寺沙耶。龍泉寺先生の娘で、私の婚約者だった」
婚約者……恋人。
エイジには想像しきれない存在だ。
でも、それは……そんな存在が自分にいたとすれば、損得などあるわけもなかった。
自分がどれだけボロボロに切り刻まれようとかまわない。
その人を助けたい。
そう思える人のはずだ。
だから象潟講介という伝説のクラッカーは人生を龍泉寺沙耶にささげた。ささげたからこそ伝説に、究極まで研ぎ澄まされて、至った。
「なぁ」
ルガモンが声をはさんだ。
「なに、ルガモン」
「ドルモン……タルタロスのおっさんと、そっちの班長のねーさんにも言っとくがな。おれは……おれとエイジは、あんたらの事情にたいして興味はねーぞ」
ウィルス種のモチーフが刻まれた球形オブジェを気にしながら、ルガモンは言った。
「…………」
「おれたちは、ダチのパルスモンと! レオンを助けるんだ! ほかのことには興味がねぇ……そういう約束だろ! さっさと話をすすめようぜ伝説のクラッカーさん!」
ルガモンはただ、いらだっていたのだ。
「責任をとれるの……!」ユーリンは魔狼に声を上げる。「あなたに責任がとれることなの……? 人類とデジタルワールドは、これ以上、深くかかわってはならない……触れてはならないものはあるのよ! ナガスミ・エイジ!」
ユーリンは若きクラッカーにも問いただした。
「しらねーな」
「しらねーよ」
ルガモンは、エイジは答えた。
「…………!」
「デジ対の班長さん。あんたの言ってることはわかる……わかるつもりだ。でも、迷子の親友を助けなくちゃならない。見つけるためにきたんだ、だから……」
「うまくやってやるさ! なぁ、エイジ!」
「おう」


モチーフを刻んだ3つの球体が、重なりあい回転しはじめる。
さながら3重連星、あるいは分子構造――それらは一定の計算式によって運動し、ひとつの立体オブジェとなる。
さらに、フロアから土台部分がせりあがってきた。
切れ目など見えない床から、ブロックがくり抜かれて上に押しだされる。
ブロックが積みあがっていく。
「って……でかっ!」
エイジはあっけにとられた。
ストーンサークル。
確か、そんな名前だったはずだ。
環状列石――ひとつひとつが数メートルもあるブロックを積んだ石柱が、円形に配置されてまわりを囲っていった。石柱と石柱のあいだには、石板が横にわたされて屋根になっている。
「遺跡……祭壇みたいだな」
エイジはつぶやく。
有名なストーンヘンジにも似ていたが、違うのはそのスケールだ。
「つーか……どこまでデカくなるんだ、これ」
「…………」
コースケはさほど気にかけたようすもない。さしたる意味はないといわんばかりに。
ズズズズッ……ン
石柱は二重三重、さらに二段三段と積まれていき……最後は非現実的な、スケールでいえば古代劇場にも匹敵する規模になった。

すり鉢状に変形したフロア。段差に囲まれたストーンサークルのステージに、3体のプロトタイプデジモンとホロライズしたパートナーの人間がいた。
「てか、寒いな。急に」
ルガモンがぶるっと体を振った。
空気が変化した。環状列石の内側だけピィンと冷気が張りつめている。
エイジは自分の肩を抱いた。
「ルガモン、ちょっとここらに炎吐いてくれない?」
「おれは焚き火じゃねぇ」
消えない魔炎は暖をとるのにちょうどよさそうだが、ルガモンはとりあわない。
ストーンサークルの中心、3相克の祭壇の前に立つ。
「フェイズ4……〝原初のデータ〟にアクセスする。さぁ、ルガモン」
ドルモンはルガモンを促した。
プロトタイプデジモンたちは再度インターフェースとして機能するのだ。
ルガモンがオブジェの前にすすむ。ドルモンはリュウダモンの拘束ツールをくわえて、引きずった。
「……ござる」
「なんだ、気づいてたんだリュウダモン」
「…………」
鎧兜のデジモンは、かすれた声でなにかをドルモンにささやく。
「なんだい? 班長さんみたいに、きみも説教か」
「おぬしは勝ち、拙者は負けた。存分にするがいい」
「潔いね。ブシドーってやつ?」
ドルモンはやや乱暴に、リュウダモンを祭壇の前に転がした。
「だが……これは、おぬしにとっても危険な選択になるぞ。ドルモン……いったい、なにが望みだ」
「おれはタルタロス……象潟講介という男に興味があった。彼と連れ添い彼に惚れた――それだけ。きみもそうだろ、リュウダモン?」
「…………!」
「いまが、コースケがおれにくれたものに報いるときだ。そして、きっと世界は変わるよ。デジタルワールドは解放される。どうなるかはわからないけど、いまよりはきっとましなはずだ」
ストーンサークルが光のシグナルで満ちていく。
「象潟さん!」
「質問は手短にな、エイジ」
応じたコースケは、珍しく気がはやっているようだった。
あせっているわけではなく、待ちきれないでいる――彼にとっての結末を。仮想モニタでコードをたたき続ける。
「〝原初の領域〟……ここのシステムにアクセスするんだよね?」
エイジたちはすでに〝原初の領域〟に転送されているが、なにかしらの機能を利用するなら、この領域のシステム的なデータにアクセスしなくてはならないだろう。
「アクセスし、利用し……可能であれば管理下に置く。無辺のデジタルワールドからDMIA患者のデジモンを発見できるとすれば、これしか手段がなかった」
「レオンのパルスモンを捜す……検索……」
「黒いアグモンの個体識別コードは私の手元にある」
「パルスモンの匂いは、おれが覚えてるぜ」
ルガモンは、パルスモンの識別コードにあたるデータをコースケに送った。
「あとは龍泉寺教授に託された、このトニックが……DMIAの治療薬がある」
コースケは注射器のデータを手に浮かべた。
「…………!」
ユーリンは肩をおとす。
理解したのだ。このSoCの作戦――オペレーション・タルタロスは龍泉寺教授も了解し協力している。むしろ絵を描いたのは龍泉寺なのではとさえ。
「賽は投げられた」コースケは自分にもいいきかせた。「ユーリン、きみだってサヤを助けたいはず。あとは見守ってくれ」
澄みわたった冷気のなか、3相克の祭壇と3体のインターフェースが無数の光のコードで接続されていく。
「すげぇ」
エイジは伝説のクラッカーを畏敬した。
人跡未踏。
さながら月の裏側――ウォールゲートのむこう側。人類が初めて〝壁〟のむこうに足跡を残した。
〝原初の領域〟そこからつながる無辺のデータへと。
挑む。
ストーンサークルを構成するブロックに無数の符号――未知の言語がびっしりと刻まれていく。
プロトタイプデジモンだけが復号化できる太古のコードだ。
「待っていろ、サヤ」
デコードプログラム起動。
3相克の祭壇がプロトタイプデジモンに同期する。
人類のツール、人の意思で〝原初の領域〟を、あまねくデジタルワールドを――
――――――――――――――――
瞬断。
すべてのシグナルは突然の停電に襲われたようにシャットダウンされた
コースケの仮想モニタ、ユーリンとエイジの視界もまた、
――おはよう、諸君。
暗転する。
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo