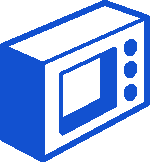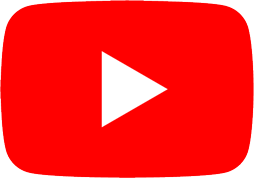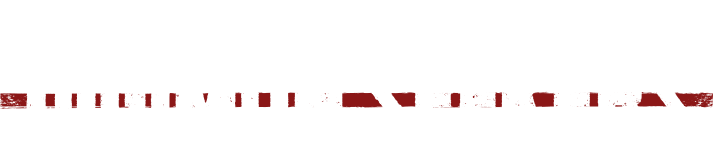-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER3
Unit 11:Digital Missing In Action
Chap.3-6
サヤのデジモンドックに記録された恐竜デジモンは、アグモン。
コースケのドックに記録されているのは、テントモン。テントウムシをベースにした昆虫デジモンだ。
ユーリンは、パルモン。外見は「頭部に花を咲かせた合成生物」とでもいうしかなく、植物と爬虫類の特徴を併せ持っていた。

実験室のテーブルでお茶を飲みながら、龍泉寺教授と教え子たちはマインドリンク後のミーティングをした。
バイオや半導体などの工場とは違って、デジモン研究にクリーンルームは必要ない。必要なのは高速ネットワーク環境、余力のあるサーバ、安定した電力供給だ。
「これで私たち3人とも予定のテスト回数をこなしたことになる」
ユーリンは工程表をチェックした。
マインドリンク――人間の精神データ、意識のデジコアへの転送。
デジモンドックで育成したデジモンを人間の感覚器官として代用すること。
「成功したのは実験室レベルのマインドリンクだ。私たちは、しょせんこのドックから出てはいないわけだが」
コースケはテントモンが入ったデジモンドックを手にした。
デジコアに意識を送ったが、そこでデジモンの視座を借りて見ているのは、ドックというせまいデータ領域のなかだけだった。
「見えたとはいってもモザイクのかかったみたいなモノクロのなにかだし、音声はノイズまみれ……」
「そのあたりは機器の処理能力を上げるしかない。ハードウェアの問題だ」
ユーリンとコースケが議論する。
「サヤたちは、まだデジタルワールドを、この目で見たわけじゃないんだよね……」
安全な実験室のドックから、いつかは踏みださなくてはならないのだ。
デジタルワールドの直接探索。
そのためにはドックのデジモンを、本来彼らが生息していたはずのネットワークに放たなくてはならない。
そしてデジモンを正確にコントロールし続ける必要がある。
どこかに逃げてしまったら、下手をすればそれっきりだ。
それこそ宇宙探査機を小惑星にピンポイントで着陸させるレベルの精度が求められるだろう。
「デジタルワールドをこの目で見ることができたとして、それは私たちが理解できるような景色なのかどうか」
ユーリンは想像した。
これが地球や外惑星とかいうのなら、想像はつく。
でも、デジタルワールドがどういう世界かは、まったくわからない。彼らが間接的に観察してきたのは数値化されたデータだけだ。
「デジタルワールドにはね、〝系〟がある」
「先生……?」
3人は龍泉寺を見た。
「いわゆる食物連鎖に近い現象も観測されている。強弱と生死の概念だ。このAI生命体はたがいに戦い、どちらかが勝ち、どちらかが負ける。負けたほうは消滅してしまうこともある。そんなデジモンたちが生息する環境とは……」
リアルワールドの地球――生態系であり生命圏。
同様に、系であるデジタルワールドを人間の五感で観測すること。これが現在の最優先課題だ。
「デジモン操縦ツールの開発は象潟くんがすすめてきた。すでに何度もデジモンを放ち、デジタルワールドを経由して帰還を果たしている。膨大な観測データをもたらしながらね」
月を周回して戻ってくるようなものだ。
カメラなんてものは積んでいないから、データは回収したデジモンを解析することで得ている。
「コースケ……率直に聞くけど、回収に失敗したデジモンはどのくらい?」
「現在のツールと航法を用いるようになってからは、成功率は80%以上になったと答えておく」
ユーリンの問いに、コースケが答えた。
100%の安全など求めようもないことだ。これは異世界への冒険、挑戦なのだ。
「人類が月を目指したとき」
龍泉寺が語った。
「――アポロ計画における最初の有人ロケット……アポロ1号、実際は4機めだったのだがね。これは発射台での訓練中、火災事故を起こした。3名の宇宙飛行士の尊い命が失われた」
「父さん」
「先生……縁起でもないこと平気でいいますね」
ユーリンは眉根を寄せた。
「無人での地球周回実験を重ねて、つぎの有人飛行はアポロ7号……これは有人での地球周回飛行に成功した。そしてアポロ8号……有人での地球と月の周回飛行。このとき初めて人類は、地球周回軌道から外れて月をまわり、月の裏側を観測するとともに名実ともに地球ではないところから地球を見た。月の地平線からのぼる地球をね。ここらへんが、われわれのデジタルワールド観測計画の現在地だろう」
地球からは決して見えない月の裏側。
ネットワークを介して、リアルワールドからは見えないデジタルワールドに達し、観測すること。
――〝タルタロス〟計画。
マインドリンクによるデジタルワールド直接探査計画は、そう名づけられた。
アポロが〝太陽〟だとすれば、こちらは〝奈落〟のタルタロスを目指して――ネットワークにもぐる。
このプロジェクトの成功が、いずれは月着陸にも匹敵するデジタルワールドへの人類の到達につながるはずだ。
偉大な一歩へと。
ユーリン、サヤ、そしてコースケに迷いはなかった。
彼らはデジタルワールドに挑む宇宙飛行士になる。
メンバーは3人。この3人のチームをおいてほかになかった。

龍泉寺電子工業によるタルタロス計画がまとまり、その日がせまっていた。
ユーリン、コースケ、サヤの3人は、計画の前日となる夜、とある場所を訪れた。
――電臨区 東京電脳大学 建設予定地
息は白く。
「ここに大学ができるんだねぇ……!」
サヤは両手を広げて、あたりを一望した。
造成工事真っただ中の、新たな東京の街だ。
視界をさえぎるビルも街路樹もない。だだっ広い更地に、まだ基礎もない建設予定地があり、重機と資材が集められている。
深夜、人の気配はない。
冴えざえとした夜の空が、東京湾を囲む都市の光に浮かびあがり、澄んだ空気のむこうに黒い窓をあけていた。
「ほんとになにもないんだな、まだ」
コースケはダウンコートのポケットに手をつっこんで、震えた。
あたりにはコンビニどころか人家さえなく、建設関係者用のプレハブの建物があるだけだ。自動販売機の光が見えたので、コースケはそっちに歩いていく。
エンジンを切ると、ユーリンは車の運転席から降りた。
社用車だ。白いライトバン。運転免許を持っているのはユーリンだけだった。
「どうして急に、こんなところに来たがったの? サヤ」
「だって見ておきたくない? ここが、私たちの将来の職場になるかもしれないんだよ」
「職場……そうね」
大学が移転統合した際には、いわゆるベンチャー村――起業支援のためのオフィス棟ができることが決まっている。
電脳大という名にふさわしくスーパーコンピューター、大規模データセンターの誘致も決まっていた。それらを利用することで、龍泉寺教授の研究はつぎのステージにすすむはずだ。
「いましか見れないじゃん、この場所……! いろんなもの……いろんな人生がいっぱいつまるはずの、なにもない場所!」
「うん……」
「10年後も、ここで、みんないっしょにいられたらいいなぁ」
サヤはデジモンドックを握り締めた。
「――見えるかい、アグちゃん。ここに新しい街ができるの。電臨区っていって……きみたちデジモンにも、きっと住みやすい街になるといいね」
小さなモノクロ画面のなかで、ドット画の恐竜――アグモンはキョロキョロあたりを警戒しているようにも見えた。
「サヤ、デジモンに話しかけてばかりいるのね」
「ユーリンはお話ししないの? パルモンと」
「え……?」
考えたこともなかった。デジモンと……話すなんて。
あとになってわかったことだが――このときユーリンたちが実行していたマインドリンクは、現在の基準であればML未達、不完全なものだった。
主たる原因は、使用していたデジモンドックの性能不足およびネットワーク通信速度にあった。
マインドリンクによって現在のようにパートナーデジモンと会話ができるようになるのは、デジタルデバイスとネットワーク処理の高速化――ハードの進化を待たなくてはならなかった。
このときサヤは、いちはやくデジモンとのコミュニケーションの可能性、重要性を見いだしていたのかもしれない。
「――犬や猫だって、話しかけるとなんとなく言葉が通じてるって思えるとき、あるじゃん?」
デジモンはしゃべれなくても、こちらの……人間の言葉をある程度理解することができたとすれば。
いまはコースケのようなエンジニアが、ツールを駆使してコマンドを打ちこむことで、デジモンを強制的に操作しようとしている。
でも言葉が通じれば、専門知識がなくても、だれでもデジモンというAIとコミュニケーションをとることができるようになる。
「そうね……そうなったら、とても便利」
「私ね! 最近聞こえる気がするんだ、アグモンの声が」
サヤは妙なことを言った。
「アグモンの……デジモンの声?」
「マインドリンクをしているとね、声が聞こえるの。だれかがサヤに話しかけているような気がして」
「デジコア内でパートナーデジモンが話しかけてくるってこと……? でも、そんな報告は……」
「そりゃ、ナイショだよ! 幻聴だとか疑われたら、計画から降ろされちゃうかもしれないじゃん」
適正不足でバックアップにまわされてしまうかもしれない。
サヤは、3人のなかでいちばんマインドリンクへの適応が遅かった。
吐いてしまうほど体調が悪化したのもサヤだけだ。
でも、そのかわり……デジコアとの融合度の指標、簡単にいえばパートナーデジモンとの相性のよさをしめすDS値は最も優秀だ。
3人のなかではサヤとアグモンのコンビが、マインドリンクによって、もっともノイズの少ない観測結果を期待できるだろう。
「アグモンは、あなたになんて言ってるの?」
「わからない。わからないけど……嫌な感じはしないかな。私の名前を呼んでね。また遊びにきたんだね、って……トモダチみたいだね」
サヤの言うことは、ふんわりしすぎていて定量的に評価しにくい。
でも、もしかすると。
デジモンがAI生命体であるなら。知性とパーソナリティを有するのであれば。
「前に、ユーリン言ってたよね」
「なに?」
「デジモンとの接触は、とてもすてきで……とても危険をはらんでいるって」
「ああ……うん。たとえるなら異星人との遭遇よね」
人類史において、デジモンは新種の生物の発見というトピックには収まらないかもしれない。
そもそもデジモンが、人類よりも文明・知的レベルにおいて格下であるというような思いこみがあるのではないか……。
ユーリンの懸念は、そういったことだ。
「人類はデジタルワールドとデジモンを発見したつもりでいるけど、発見されたのは人類のほうかもしれない」
サヤも、その問題を認識していた。
「であればこそ、確かな観測の継続が必要になる。リアルワールドとデジタルワールドは、もうネットワークによってまじわってしまったのだから」
溶けあってしまったコーヒーとミルクは分離できない。
人類とネットワークを遮断してデジタルワールドを放棄することなど、不可能なのだ。
「やっぱり、父さんにいちばん必要な人はユーリンだね」
サヤは笑った。
「コースケじゃないの?」
「ううん、あいつは父さんに似ているだけだから。私は……娘だし、いまさら他人になることはむずかしい。あなたがいるからこのチームは、なんていうのかな……会社として成りたっている」
「…………」
「たとえばだよ? もし私たちがデジタルワールドの研究で道を誤るようなことがあったら。それをふせぐことができるのは、ユーリン……あなただけ。そんな気がする」
「ごめん、ちょっとよくわからない」
「うん……そうだね」
「あー、寒い。あの自販機、なんで真冬に冷たいの入れてんだよ」
グチグチ言いながらコースケが戻ってきた。
ふたりにホットのドリンクを渡す。
「寒い……風、強いし。ねぇ、気がすんだなら帰ろう」
ユーリンは自分の肩を抱いて震えてみせた。
「もうちょっといようよ」
「私は、別にかまわん。こんなふうにボーっとするの、久しぶりだ」
「私、車のなかにいるから」
ユーリンは車内に戻った。
エンジンをかけて暖房を入れる。
サヤとコースケは……寄り添って、ずっと空を見ていた。
月だけが見える夜。
ユーリンはハンドルに手を置いて、フロントガラス越しにふたりを見ていた。
――なんなのかな、これは。
見せつけられているようで、ちょっと腹が立ったユーリンは、こっそりふたりの姿を携帯のカメラに収めた。


龍泉寺電子工業、第4実験室。
タルタロス計画実行当日。
龍泉寺教授の指揮のもと、ユーリン、コースケ、サヤで構成されたアタックチームが、AI生命体デジモンのデジコアに精神データを転送する。
3人同時のマインドリンク。
ユーリンは船長、コースケはエンジニアであり機関士・航海士、サヤは探索にあたる観測員。
3人の意識は、それぞれのパートナーデジモン(パルモン、テントモン、アグモン)とともにデジタル仮想観測船〝タルタロス〟号に乗りこんだ。
マインドリンクによるデジタルワールドへの直接探査が、ついに開始された。
そして――
失敗した。
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo