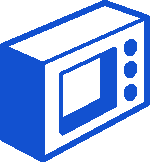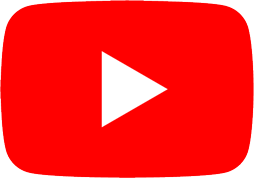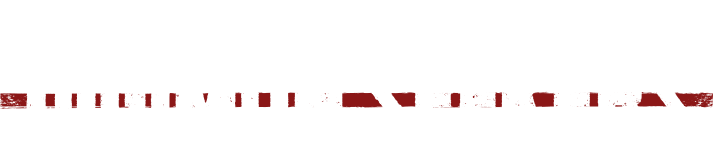-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER3
Unit 11:Digital Missing In Action
Chap.3-5
龍泉寺は助教授から教授になった。
このころにはメガテック企業からも出資の話を受けて、会社の設備は起業時とは比べものにならないほど拡大していた。
龍泉寺電子工業は、いよいよベンチャー企業として軌道に乗りはじめる。
スタッフの数も増えた。
場所はあいかわらず工場跡を借りていたが、手狭になって引っ越しを考えなくてはならなくなったほどだ。
「早いね」
ユーリンたちは、まだ大学生だ。
けれども龍泉寺教授と出会ったことで、はるかに速いスピードで人生をすすめていた。その実感はある。
デジタルワールドと、あの、小さな〝怪物〟――デジモンと出会ったことで。

「デジタルワールドは人生を変えるね」
サヤが笑った。
変わったことといえば……サヤの指に指輪がはめられていた。
「おめでとう、と言うべきなのかな」
「お祝いしてくれていいんだよ~?」
婚約指輪だそうだ。
「おめでとう。あのズボラ男のコースケが女に指輪のサイズを聞いて贈るとか、それだけで私は胸がいっぱいだわ」
「でしょー」
サヤはさりげなく自慢げだ。
やはりデジタルワールドは……人と人生を変えるのかもしれない。
「でも……ほんとに人が増えたなぁ。いろいろ気を使うし」
「新しい役員の人、どう? ユーリン」
出資を受けた企業から非常勤の役員を迎えるようにもなった。
「基本、監査とかコンプラの人だから……。まだまだ何年も先の話だけど、龍泉寺先生は上場する考えもあるみたい」
そのためには大学の龍泉寺研究室ではなく、町工場みたいな龍泉寺電子工業でもなく、企業としての体裁を整えなくてはならない。
「サヤはさ、経営とかよくわからないけど……出資した人たちは上場しないとお金を回収できないもんねー! なんたってわが社は創業以来、ぶっちぎりで大赤字をたれ流しまくってるんだから」
それはそうだ。売上はほぼゼロ、利益はゼロ以下だ。
「そりゃ、だからベンチャーなんだし」
「ねー」
「だからっていまの……飛ぶ鳥を落とす勢いの龍泉寺教授の、研究のジャマはしないでしょ。彼らにとって先生は金のタマゴを産むガチョウ……」
「サヤ!」
工場の建物から、コースケが小走りで出てきた。
「よ、色男」
「なんだよユーリン、いきなり冷やかしか」
コースケまで、まんざらでもない顔になった。ノロケている。
「こんなかわいいサヤを、かどわかしやがって」
ユーリンは、なんだか納得がいかない。
コースケは、近ごろはヒゲを毎日剃るようになった。ナマイキにもジャケットなんか着て色気づいている。
「人を犯罪者みたいに言うな……! それより……見ろ! こいつを!」
コースケはヘルメットみたいにごついVRモニタを手にすると、サヤの頭にすぽっとかぶせた。
「ふごっ……なに?」
「なに、なんなのよ?」
ユーリンが問いただす。
「ついに実現したかもしれない……! 見えるかサヤ……そいつは……」
「見える……見えるけど、なんだかよくわからない! なんなのこれ!」
VRモニタをかぶったサヤは困惑する。
色はない。モノクロだ。
昆虫の複眼から見た映像を、仮想的に再現した映像のようでもあり。
でも、確かにそれが――なんらかの生物の〝視座〟に立った映像であることは直感でわかった。
「それは世界初の……デジモンの視覚からとらえた映像だ! それがデジモンの目なんだ……!」

さらなる成果を求めて、龍泉寺教授は研究をつぎのステージへとすすめた。
目指すはデジタルワールドの直接調査。
現実世界――リアルワールドとは成り立ちが異なるネットワーク上のデジタルワールドは、そのままでは観測プログラムに記録された膨大な数値データでしか認識できない。
なんとかして、人間の五感でデジタルワールドに触れることはできないのか……?
見たい、聴きたい、嗅ぎたい、味わいたい、触れたい。
その可能性を追求した結果、AI生命体デジタルモンスターの構造の核をなす〝デジコア〟と呼ばれる部位に、人間の意識を転送することで、デジモンを介して限りなく本物の〝体感〟ができるのではないか――という仮説のもとに研究がすすめられた。
技術の土台はあった。
人間の精神、記憶のデータ化についての研究は、すでに脳科学をはじめとした分野ですすんでいた。
具体的には、個人の記憶データをもとにしたパーソナルAIの開発。
視覚、聴覚、運動神経などの不具合を治療する、脳と各種センサー、電子デバイスを直結させたニューロモデレーション。
それらとロボティクスを融合させた人体補完型アンドロイドの開発……。
それら〝ゼロから人間を造る〟ことを究極目標とした分野は、きびしい倫理的な壁、法規制によって10年、20年後もなお研究段階の域を出ないのだが……。
デジタルワールドには、それら倫理の壁はなかった。
すべては、いわばデジタルデータ上のシミュレーションにすぎなかったからだ。
デジモンを、デジタルワールドにおけるVRカメラのように利用することはできないだろうか?
ただのカメラではない。すべての五感をデジモンと人間とのあいだで共有する。
デジモンがAI生命体であればこそ、すべての感覚をデジタルデータとして取得できるはずだ。
あとは人間が、人の意識がデジタルワールドに歩み寄ればいい。
デジモンのデジコアに人間の意識を移す。
「――退屈しなくてすみそうですね、死ぬまで」
龍泉寺教授は笑った。
この研究テーマをすすめるかぎり退屈なんかしている暇はないだろう。
マインドリンク技術の基礎が、龍泉寺電子工業でひそかに開発された。
リスクと倫理の問題をクリアすれば、それは不可能なこと、オカルトではなかった。

龍泉寺沙耶は、世界で初めてデジモンとの意識のリンクを果たした人間のひとりだ。
――第**回マインドリンク実験、終了。
ユーリンがアナウンスした。
龍泉寺電子工業・第4実験室。
歯医者にあるようなフレキシブルに稼働する座席シートに、被験者――サヤが体を横たえている。
内装は古い工場のままなので、なんとなく退廃的な、サイバーパンクの世界にありがちなヤバい町医者の診療所に見えないこともない。
「バイタルセンサー、チェック」
「心拍、血圧、体温、すべて正常」
モニタチェックをしてコースケが答えた。
サヤはヘルメット状の機器をかぶっている。
一種の脳波測定器だ。全身に取り付けられたセンサーでバイタルチェックが行われてモニタリングされている。
サヤの脳が受け取っている情報は、彼女とマインドリンクしたデジモンを介してもたらされたものだ。それらの全情報をリアルタイム処理するには、いま会社にある機材をフル稼働させなくてはならなかった。
「――DS値低下。被験者の意識レベル回復。マインドリンクが解けるぞ」
コースケが告げた。
ユーリンはおもむろにバケツを持ってシートに歩み寄った。
ぴくん、と被験者が痙攣する。
サヤが意識を回復した。
「ふぅ」
うーんと手を伸ばす。足をバタバタさせる。
そうやって肉体の感覚をおさらいするみたいに動かすと、体を起こして頭にかぶったセンサーを脱いだ。
「はい」
ユーリンがバケツを差しだした。
「うぷっ……でも、もう、慣れたっぽい」
サヤはちょっとつらそうな表情で笑った。
初めてマインドリンクに成功したとき、彼女は、父親と親友と婚約者の前で吐瀉物まみれになってしまったのだが……。
パチパチ……
龍泉寺教授が拍手した。
「マインドリンク後、再度マインドリンクを実行するときは充分な休息が必要になる。マインドリンクには後遺症のリスクがある。だが、慣れることができる。その可能性が見えてきただけで今回も大成功だ」
第4実験室には会社の創業メンバーが集まっていた。
龍泉寺教授、ユーリン、コースケ、サヤの4人だけだ。この実験室の出入りにはセキュリティパスが必要で、マインドリンクのことは社内でもまだ機密だった。
「おつかれ、アグちゃん」
サヤはシート脇の機器と接続したガジェット――デジモンドックを手にした。
――〝アグモン〟
モノクロの小さなモニタに、ドット画でデジモンが表現されていた。
文字どおり小さな〝怪物〟――その姿は二足歩行の肉食恐竜をベースにしている。
ネットワーク探索で発見されたデジモンの数と種類は、現在進行形で、世界中でどんどん増えている。
デジモンには種類がある。いずれはこれらを分類、系統化する作業も必要になるだろう。
龍泉寺教授は採取したデジタマから誕生、選別した3体を、教え子たちに1体ずつ渡して育成を任せていた。
ユーリンたちは情報を交換しながら、デジモンドックでデジモンを育成している。
デジモンの育成を始めて大きな変化があったとすれば……コースケが、前よりも規則正しい生活をするようになったこと。なにしろデジモンは世話とメンテナンスをおこたると、すぐに死んでしまうからだ。
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo