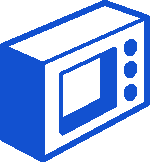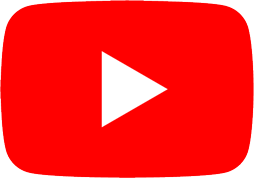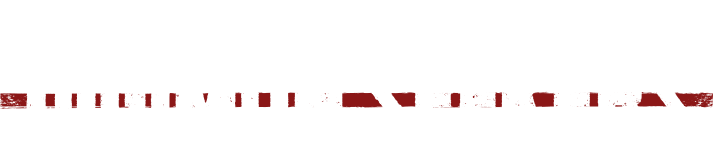-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER3
Unit 11:Digital Missing In Action
Chap.3-4
――「龍泉寺電子工業」
工場の倉庫扉に、いかにも仮といった感じで会社名がペイントされていた。
このあたりは電臨区構想にふくまれていて、いずれ再開発が行われるはずだが、それまでの期間という契約で借りることができた。
「よっ……と」
サヤが郵便ポストに名札プレートを追加して貼る。
――「東京電脳大学(仮) 龍泉寺研究室」
統合移転後の大学名も、ようやく決定したのだ。
「東京電脳大学……東電大?」
サヤはさっそく略そうとする。
「それじゃ電力会社みたい。電脳大じゃないかしら」
ユーリンは笑った。
電臨区の開発は、まず大学や研究機関などの独立行政法人、そのほかの公共施設の新設移転から始まる。
その後に民間企業の誘致、商業施設、高層マンションの建設などがすすめられることになる。同時に地下鉄、新交通システムなどインフラ整備によってカタチになりはじめるだろう。
10年後には、まったく新しい区がひとつ東京に誕生する。
電臨区はさまざまな特区に指定されて、全世界から人と資金が集まる国際都市になるはずだ。きっとなる。
「先生、近ごろうれしそうね」
「晴れて一国一城の主だもん! 借金いっぱい背負っちゃったけど」
それは娘のサヤにとっても無関係な借金ではない。
龍泉寺電子工業の起業にあたっては、大学ベンチャーキャピタルと政府系ファンドなどから融資を受けた。
さらに龍泉寺助教授は自己資金で出資した。経営の主導権を考えてのことだが、そのために少なくない借金をしている。
「とにかくお金がかかるもの、この研究は」
ユーリンはため息をついた。機材の費用はもちろん、24時間、湯水のように電気を使う。
「研究内容は父さん……先生主導。ここはゆずってない」
「まぁ、理解できる人もいないでしょうしね。デジタルワールドなんて……」
ネットワークのむこうにはデジタルの異世界があった。
そんなことは空想で、税金で研究することではない。
資金を引っぱるにあたっては自律型AIの研究、VR技術開発といった時代に合わせたテーマを立てる必要があった。どちらも簡単にはビジネスにできないが、研究しないわけにはいかない分野だ。
でも、龍泉寺研究室のメンバーは確信していた。
このネットワーク上で発見されたAI生命体の研究が、人類にとって、新たな可能性を開くことを。


「――見たまえ! これが試作したAI生命体記録用外部記憶装置、
通称デジタルモンスター・ドック・システムだ!」
龍泉寺助教授が試作品のガジェットを発表した。
龍泉寺電子工業のオフィスは、工場だった建物の一室を利用している。
サーバ室は別にあるので、以前の研究室と比べればずいぶんさっぱりした。
どこぞのウェーイと仕上がったベンチャー企業みたいな、華やかな受付嬢とか和気あいあいとしたラウンジ、無料食堂、充実した福利厚生なんてものはないが。
「デジタルモンスター……?」
ユーリンはきょとんとした。
「長いから略してデジモンドックね」
サヤが略した。
「なんだか、おもちゃみたいですね」
ユーリンは率直な感想を返した。
ガジェットのサイズはタバコの箱より小さい。モノクロ液晶画面と操作用のボタンがついている。
「商品化するわけじゃないから。先生の趣味丸出しなわけ」
コースケが言った。
龍泉寺はガジェットマニアでもあり、携帯電話やレトロなゲーム機などガラクタの収集癖がある。
龍泉寺智則と象潟講介。
この天才肌のふたりにも役割分担はあって、コースケは生粋のプログラマなのに対して、龍泉寺は電気工学のエンジニアよりだ。
「まさに……! これはトイ――おもちゃとしての展開すらあり得るよ。愛玩用のデジタルペット飼育器としてね」
龍泉寺の言葉に、みな注目する。
「――そもそも、われわれはこの小さな〝怪物〟デジタルモンスターを、長時間保存、飼育することができずにいた。このAI生命体は、たやすく死んでしまうからだ。思うに……われわれ人類のネットワーク環境は、彼らデジモンにとってはストレスなのではないか……? 私は、デジタルワールドと近い環境を再現することが、このAI生命体の活動維持の条件だと考えた」
研究のことになると龍泉寺の独演会はとまらない。
ユーリンたちは大学の講義よりも長い話を聞かされることになった。
でも、まったく退屈はしなかった。
龍泉寺の話には――常に〝夢〟があったからだ。
もしデジタルモンスターを、子供がデジタルペットとして飼育するような世界が来たら……。
――デジモンが、人類の、かけがえのないトモダチとなることだってあるだろう。
龍泉寺は新しい世界を語った。
「デジモンが友達……?」
ユーリンは想像をめぐらせる。
とてもすてきだと思えた。
そして、とても危険をはらんでいる。
そんなふうに先まわりをして心配の種を増やす自分の性格をユーリンは自覚していた。
「じゃーん」
サヤがなにかを見せた。
おなじガジェット――デジモンドックだ。違うのは、モノクロ液晶画面になにかが映っている。
「タマゴ……?」
ユーリンの目には、それがタマゴに見えた。
「そう! これはデジタルモンスターのタマゴ……略して〝デジタマ〟!」
サヤはデジモンドックを大事そうに両手で持った。
「デジタマ……」
「ネットワークを探索していたら、偶然このデータを発見したの!」
「このドックは仮想的にデジタルモンスターを可視化できる。目で見ることができるんだ。データと数値の羅列ではなくね」
龍泉寺が説明した。
「すごい……!」
ユーリンは感動した。
「おい……なんか、そのデジタマ、動いてないか……?」
コースケが言った。
「?」
「まさか……うまれるのか!」
「あ! ちょっと父さん」
龍泉寺は声をひっくりかえして、娘の手からデジモンドックをひったくった。

デジモンドックの開発によってAI生命体を安定して保存、ある程度育成することが可能になった。
研究は飛躍的にすすんだ。
AI生命体は正式にデジタルモンスター、デジモンと名づけられる。
そのうちスポンサーが潤沢な資金を持ってやってくるようになった。
ネットワークにおけるデジモンAIとその応用が、10年後、20年後の世界のパワーバランスの鍵を握る可能性があったからだ。
世界を、ある程度予見できる者にとっては自明だった。
デジモンが生命体であるか否かの議論はさておき――そんなことはどうでもよく、デジモンのAIとしての実用性に疑いはなかったからだ。
豊富な資金力によって、龍泉寺は学内でも学会でも立場を強めていく。
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo