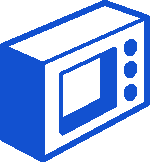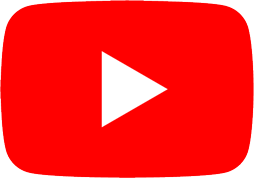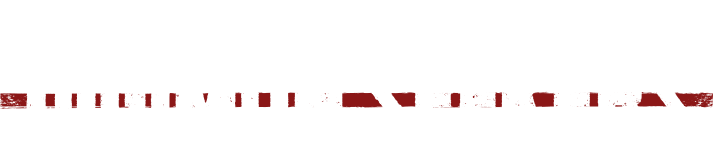-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER3
Unit 11:Digital Missing In Action
Chap.3-3
発見まもないデジタルワールド研究の先頭を行く龍泉寺研究室の主要メンバーは、まだ学生の3人。
徐月鈴。
象潟講介――天才プログラマ。
そしてユーリンの親友である龍泉寺沙耶(サヤ)、龍泉寺助教授の娘だ。

「――サヤはコースケを甘やかしすぎなの。着替えを取りに家まで行くなんて、まるきりお母さんみたいじゃない」
豚丼をパクつき、ユーリンはペットボトルのお茶をゴクゴク飲んだ。
「そこは奥さんでしょ。いいじゃん、ついでだったし」
「あなたの人生の1時間でも、こんなズボラ男のために使うのは損失だって言ってるの」
「ふーん……はいコースケ、豚汁」
「ありがと」
「サラダも食べなきゃだめだよ」
などと言葉をかわすコースケとサヤの姿は、まるで新婚夫婦で。
娘と、目をかけている男子学生の仲むつまじいようすに、龍泉寺はのんきに笑うのだった。
ここは龍泉寺家の食卓か……。
ユーリンは所在ない居候みたいな気分になる。
「はっはっは」
「なんですか、先生」
ユーリンはつい笑いの意味を深読みしてしまう。
「彼女は……ユーリンはね、われわれみたいに生活力に欠陥がある男を生理的に受け付けないんですよ、先生」
「そうかね象潟くん。ところで、われわれとはいったいどういう……」
「はーい、だまって食べようね野郎ども。サヤちゃんが、わざわざおまえらのエサを買いだしにいってきたんだから」
サヤのひと言で、みんな、はーいと笑顔になってごはんを食べた。
食後の話題といえば、いつも研究のことばかりだ。
デジタルワールド。
ネットワーク上で発見された〝異世界〟と謎のAIプログラム。
龍泉寺研究室は、世界に先んじて、その〝生命体のように振る舞うプログラム〟を観測した。
それはまるでデジタルの世界の小さな〝怪物〟たち。
しかし、そのAIプログラムは短い期間で消滅――死んでしまうため、研究は思うようにすすまなかった。
このAIプログラムを育成、飼育するにはどうすればいいのか。それが目下の研究課題だ。
「――もし先生の仮説どおり、これがデジタルワールドに生息するAI生命体なのだとしたら」
サヤが言った。
彼女は、龍泉寺助教授に対しては「先生」だったり「父さん」だったり、わりと呼び名がぐちゃぐちゃになりがちだ。
龍泉寺助教授本人も、そうしたことを気にするタイプでもない。家族は愛しているが、すべての生活がまず自分の研究のためにある。よくいる学者タイプだから。
「AI生命体……とすればペットみたいに飼えるってことだね。たとえば、このコを」
龍泉寺はモニタをしめした。
画面にデータの数値が羅列されている。それが、なにかしらの法則性――意図をもって変化している。
「かわいいですね、こいつ」
「そうだろう、そうだろう象潟くん。私が思うに、このコは……うん、両生類っぽいかな」
「ああ、わかります。2面性というか……」
「そんなのわかるの、あなたたちだけですよ」
数値の羅列を愛でるふたりに、ユーリンはあきれた。
「でもさユーリン。もし、このデータをだよ……数値じゃなくて、この目で見られたら。観測できたら」
サヤは夢見る。
きっと世界の常識はひっくりかえるだろう。
地球外生命体は、火星でも、木星や土星の衛星でも、ほかの星系の地球型惑星でもアンドロメダ星雲でもない。ネットワークの世界にいた。
「そうなんだ、サヤ」龍泉寺が娘を見た。「これからデジタルワールドの研究を大規模にすすめるためには、まさに目で見てわかることが重要になる」
「ようは……政府なり企業なりに出資してもらうためには、おれたちだけじゃなく、彼らにわかるように研究成果をアピールしなくちゃならない。残念ながら、このデータの美しさは一般の人間には伝わらないからな」
コースケが補足した。
「まぁ、それはそうね」
ユーリンは同意する。
「そこでだ」
龍泉寺はいかにも本題です、といった口ぶりになってテーブルで両手を組んだ。
そうしたときの彼は、とても重要なことを話すことをユーリンは知っていた。
「はい」
「起業することにした」
言葉の意味が、ユーリンはとっさにはわからなかった。
「きぎょう……起業ですか? 会社を?」
「私はデジタルワールドをこの目で見たいんだ。この耳で聴き、この手で触れて……」
「あー、先生。それは話がぶっ飛びすぎ……」コースケが代弁した。「あのなユーリン、大学の起業支援制度があるだろ? それを利用する」
「大学ベンチャーキャピタル……? 大学の資金援助を受けて株式会社・龍泉寺研究室をつくるってことかしら」
「そう。いまの内閣はスタートアップ支援に熱心で……予算がつけられそうなんだ」
コースケが説明した。
「コースケ……サヤも知ってたのね? 知らなかったのは私だけ?」
「サヤもね、さっき聞いた」
「ヘソを曲げるな。いろいろ順序ってものがあった。先生だって、おまえらにぬかよろこびはさせたくなかったんだ」
コースケはすねるユーリンに言って聞かせた。
「ぬかよろこびって?」
「クーラー効きすぎの、このオンボロ研究室からおさらばできる。サーバ室完備のオフィスに移れるぞ」
「OK、賛成」
ユーリンは脳で考えるより先に同意した。
「そこで! 予算獲得のために、スピーチとプレゼンが得意なトリリンガルのユーリンの出番ってわけだ」
「頼りにしてま~す」
コースケとサヤはユーリンの機嫌をとりはじめた。
龍泉寺とコースケは、まぁ典型的な研究者脳だ。
サヤはユーリンよりはるかに成績もよい英才だが……見た目の印象がコドモすぎるのはいなめない。深夜、中学生と間違われて、しょっちゅう警察に補導されかけている。
「でも、大丈夫でしょうか」
ユーリンは龍泉寺にたずねた。
「なにがだね」
「私は生まれたときから日本人ですが、父親は帰化人です。母もルーツは……」
デジタルワールド研究は最先端分野だ。
ネットワークとサイバーセキュリティ、すなわち国防にかかわる技術開発となるだろう。ベンチャーに国費を投入するのであれば産業スパイがらみのチェックはある。差別というわけではなく、国籍もまったく無関係ではない。
「それに、なにか問題が?」
龍泉寺はユーリンの目を見た。
「ユーリン」コースケが言った。「先生は、おまえしかいないって言ってるんだ」
「…………! はい!」
龍泉寺研究室は動きだした。
モニタで活動しているデータの数列……デジタルワールドで発見捕獲された、小さな〝怪物〟の正体を解き明かすこと。
「これから、忙しくなるぞ」コースケが言った「おれは先遣隊として、新しいオフィスにいることが多くなる」
「オフィスの場所も決まってるわけね」
「コースケ、大学はどうするの? 単位ぜんぜん取ってないんじゃ?」
サヤは心配した。
「まだ何年かは籍を置けるさ。卒業する必要があるわけでもないしな」
「卒業できなくても、象潟くんなら雇ってあげるから」
龍泉寺は機嫌よく笑った。
ユーリンはため息をついた。
「先生……それは教育者として、あるまじき発言では」
「ふむ」
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo