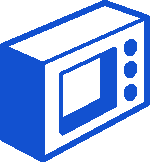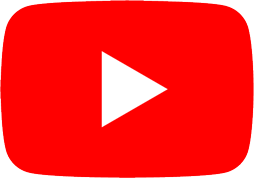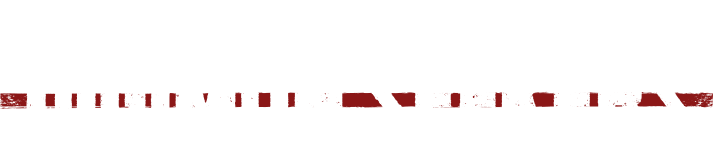-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER3
Unit 11:Digital Missing In Action
Chap.3-2
――われらは法と職務のために。
――なにものをも恐れず、なにものをも憎まず、良心のみにしたがい……。

警視庁。
生活安全部サイバー犯罪課捜査第11係デジモン犯罪対策チーム、略称〝デジ対〟――
班長の徐月鈴はパートナーデジモンとマインドリンク、今日も無法のネットワークをパトロールする。
――〝縦横車(じゅうおうぐるま)〟!
まさに縦横無尽、高速飛行からの全包囲攻撃でクラッカーたちのデジモンは一網打尽にされた。
犯罪者たちを見おろしたのは1体の完全体デジモンだ。
東洋の龍を思わせるボディ。
美しいデジモンだった。黒地に金のヒゲと縁どりは工芸品のようで、重厚な鱗の鎧をまとい両手には宝玉をにぎっている。
――ヒシャリュウモン 完全体 獣竜型 ワクチン種
ユーリンのパートナー、リュウダモンの進化した姿だ。
「クラッカーを制圧……」
「さすが班長、お手並あざやか!」
パートナーデジコアにいるユーリンに警察無線(チャット)が飛んできた。
「おせじはいいから処理班を呼んで、サツキ」
「了解~」
副班長の玉姫紗月はいつもの軽いノリで応じると、彼女のヌメモンでクラッカーにダメ押しのキツい一撃を喰らわせつつ、回収班をむかわせた。
ここはネットワーク、某官庁のサーバ。
サイバー戦争は日常だ。
政府機関には世界中からクラッキングがしかけられている。これらデジモンを用いたサイバーテロ対策は、日本では主として警察があたることになっていた。
なぜなら彼女――徐月鈴が警視庁に奉職しているからだ。
公安部や防衛省では、未だに充分なカウンター・デジモン部隊が未整備だった。日本のデジモン犯罪対策は徐月鈴なくしてはあり得ない。それほど彼女個人の能力に依存しているのが現状だ。

ヒシャリュウモンが制圧したクラッカーのデジモンのそばに降り立つ。
ユーリンはホロライズして、かたわらに立った。
「どう、ヒシャリュウモン?」
「手慣れたものでござるな。データ回収用のサイボーグ型デジモンばかり」
ヒシャリュウモンは押収したデジモンを解析する。
「ええ、そうね」
「ねらいが国家機密であるなら……退避行動などのツールの癖からして、やはりかの国のものでござろう」
ヒシャリュウモンは推測した。
その分析が、どんな専門家よりもすぐれていることをユーリンは知っている。
「イタチごっこね」
「まだ動けるデジモンもいるようでござる。どうでしょう、ひとつふたつ、みやげを持たせて帰してみては?」
「仮に犯人がわかったところで、私たち警察の出番はないけど……」
外交問題となれば警視庁の出る幕ではなくなる。
デジ対は、間違っても他国のサーバに先制攻撃などできないのだ。現行法では。
「左様でござるか」
「でも、おねがい。彼らのデジモンが、彼らの国に帰ってどうなろうと関係ないしね」
腹いせに毒まんじゅうのおみやげを持たせるくらいの遊び心はある。
「御意」
ヒシャリュウモンはうれしそうに、クラッカーのデジモンを拘束したのちに適切な処置をほどこしはじめた。
ヒシャリュウモンのひたいのインターフェースを見ると、ユーリンは思いだす。
おなじインターフェースを持ったデジモンの所有者のことを。
(コースケ……あなたはいまどこで、なにをしているの。あなたのデジモンと)…………

永住瑛士が誕生するよりも以前の過去に、この物語はさかのぼる。

徐月鈴の学生時代。
彼女が籍を置く大学は、ネットワーク上で発見されたばかりの「謎のAIデータ」の研究において、世界に先んじていた。
ネットワーク上には現実世界とは違う異世界があるらしい。
未知のAIプログラムが、さながら生命体のように振る舞っている。
そもそも人は――ネットワークは人類が発明して発展させてきたものだと、あたりまえに考えていた。
ところが、だ。
さまざまな観測データの積み重ねによって、ひとつの仮説がたてられた。
――ネットワークが人類の発明それ以前から存在していたとしたら……?
人類はネットワーク上の異世界にアクセスする手段を、ようやく発明したにすぎないのだ……と。そして人類が探し求めてきた地球外生命体もまた、すでにデジタルデータとして存在していたのではないか。
異世界デジタルワールド。
その発見と調査に、きわめて重要な実績を上げてきた研究者のひとりが、龍泉寺智則だ。
龍泉寺研究室で中心的な役割を果たしていたのは、まだ大学生だった3人――気鋭の若者たちだった。

新時代にむけた電臨区構想がまとまり、東京の湾岸地区では鉄骨とコンクリート、あらゆる資材が集積されて、ダンプカーと重機が行きかう都市改造工事が始まっていた。
首都は、大きな変貌を遂げるだろう。
数年後の電臨区への移転統合が決まったこの大学のキャンパスと建物も、いずれ、きれいさっぱりなくなる。そう考えるとユーリンはふしぎな感じがした。
龍泉寺研究室。
ここはとにかくエアコンがガンガンに効いて風がめぐっている。スチールラックに積まれた大量の機材の放熱を抑えこむためだ。
「おはようございます、龍泉寺先生」
もう夕方だが、この研究室はいつでも「おはようございます」だ。
「おはよう、ユーリンくん」
奥の席に腰をすえた助教授――龍泉寺はモニタを注視しながら声を返した。
「これ、届いてましたよ」
ユーリンは郵便物の束をちらかった机に置いた。
「ふむ」
龍泉寺はいつもの生返事で。
いつからそうしていたのか、モニタとにらめっこして作業に没頭している。
「渡しましたからね、郵便物! あとになってまた、渡した渡してないは嫌ですから、いますぐ確認してください」
「ここだ……だれだ、こんなクソコードを書いたやつは!」
「ご自分でしょう」
「…………? そんなはずは……そうなのか」
履歴を見ればわかることだ。
「――先生、サーバ室の設置申請、まだとおらないんですか……? 寒すぎですよ、ここ」
ユーリンはイスにかけてあった上着を羽織った。
「数年後には大学ごと引っ越しだからね。いまは、ささいなものでも設備投資をしたがらないんだ」
「ただでさえ電気代の使いすぎで、にらまれてますからね、うちは」
「まったく……この3年、これからの3年が重要だというのに」
龍泉寺はボヤきがとまらない。
「世界では、この分野の研究にひそかに資金をつけはじめているって聞きます。ケタ違いの」
「いま、われわれが持っているアドバンテージなど、たちまち埋められてしまうだろう」
「海外に先を越されたら、どうするつもりなんでしょうね政治家は……? いっそ外国行きましょうか、先生なら引く手あまた……」
「おいおいユーリン。国の宝をむざむざ外国に売るつもりか」
声が飛んだ。
スチールラックのあいだにパイプ椅子を3つ並べて、だれかが横になっていた。
「コースケ、いたの」
ユーリンは年上の男子学生を呼び捨てにした。
「泊まりこみだ」
もう何日、家に帰っていないのだろう。コースケは無精ヒゲを伸ばして、おとといとおなじ服を着ていた。
象潟(きさかた)講介――龍泉寺研究室の一員だ。
「とりあえず顔洗って歯をみがいてきて。着替えはないの?」
「あー、それは……」
と、研究室のドアが開いた。
「はーい、エサだぞ野郎どもー」
ミーティング用テーブルの上にあったものが押しのけられて、テイクアウトの牛丼が積まれる。
「おー、腹減ったわ」
「はいコースケ、これ着替え」
研究室に入ってきた小柄な彼女が、服を入れた紙袋をコースケに渡した。
「サヤ……あなた、コースケの家まで着替えを取りに?」
「うん! ああ、ちゃんとユーリンのぶんもあるよ。ユーリンは豚丼だよねー」
サヤと呼ばれた彼女はテイクアウト用のどんぶりをひとつユーリンによこした。
「ありがとう……あ、お金」
「いーの、これは父さん……先生のおごり。豚汁もついてるよ」
「え? 珍しい」
龍泉寺を見て、ユーリンは少しびっくりした。
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo