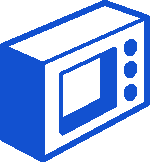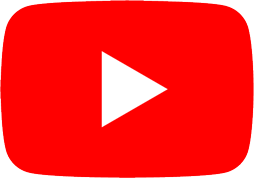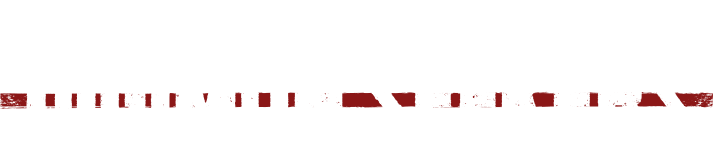-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER3
Unit 11:Digital Missing In Action
Chap.3-11
「――象潟だ。象潟講介」
男は名乗った。リアルの名前だ。
「きさかた……」
「いいのかコースケ? そこまで話して」
ドルモンは懸念した。
エイジを警戒しているというよりは、ドルモンはだれに対してもこういうスタンスなのだろう。
俺様上等のルガモン、やんちゃっぽいパルスモンと比べて、シビアな性格らしい。
「フェアじゃないさ、私だけが彼を知っているのは」
「情報の非対称性があるからこそ交渉になると思うけど……」
「珍しい名字ですね」
ドルモンがしゃべると話がめんどうになりそうなのがわかって、エイジは男に話題を振った。
「ルーツは東北らしい。漢字はゾウさんの象に新潟の潟。長いことネットワークの世界で生きてきた。この名前を使う機会もあまりなくなったが」
GriMMの発展によって、ネットワーカーは経済的にもオンラインで完結する時代になった。本職のクラッカーにとっては、クラッカーネームやアカウントのほうが本名のようなところがある。
「で、タルタロスのおっさんが捜しているのは、だれなんだ?」
ルガモンがたずねた。
「さっき大切な人って言ってたけど」
エイジは男――象潟の反応をうかがった。
「私が大学生だったときの話だ」
「って……けっこう昔じゃ?」
「話が長くなりそうだな」
ルガモンはぺたんとおすわりした。
「デジタルワールドの発見、デジモンの発見とデジモンドックの開発、マインドリンク技術……エイジ、きみが生まれる前から、それらは達成されていた」
そんな昔から……。
エイジはちょっと驚いた。
デジタルワールドの歴史については、学校で学んだり、どこかの動画で5分でわかるようにまとめられているわけではない。また、その真偽も確かめようがなかった。
「私は最初のマインドリンク実行者のひとりだったはずだ。主としてハードウェアの性能による制約から、マインドリンクはいまよりも精度の劣る、より危険をともなう未熟な技術だった」
細かい話ははぶく、と言って象潟は続けた。
「――おそらく世界初となる、マインドリンクによるデジタルワールドへの直接探査計画。私はプロジェクトメンバーのひとりだった。その計画の実行中、DMIA――当時はその用語すらなかったが、同行した仲間がデジタルワールドで行方不明になった」
マインドリンクしたままパートナーデジモンごと失踪した。
エイジのなかで象潟講介への警戒心が薄れていった。
かわって、あふれだしたのは……共感。
(この人は……おれとおなじ?)
彼は――
伝説のクラッカーであるタルタロスこと象潟講介は、それからの人生をDMIAになった仲間を救うために費やしてきた。
それがタルタロスの〝物語〟――
「それが、私がクラッカーになった理由であり、すべてだ」
象潟は仮想モニタをひらいた。
GriMMの掲示板。情報募集のトピックに、エイジも知っている話題があった。
「〝黒いアグモン〟……!」
エイジは、そのときわかった。
1億DCという破格の金がかけられたデジモンの捕獲案件。マーヴィンは、この懸賞金はリーダー・タルタロスのポケットマネーだと言っていた。
「黒いアグモンは、DMIAになった私の仲間のパートナーデジモンだった」
リーダー・タルタロスは、DMIAになった仲間のデジモンを捜していた。
「おっさんの仲間は……ええと、リアルワールドの肉体のほうな。それから、ずっと植物状態のままか?」
ルガモンはたずねた。
「そうだ」
いまは海外の専門の施設にいるという。
DDLの医療室にいるはずのレオンも、いずれはそうした施設に移さねばならなくなるのだろうか……。
いいや、そもそも肉体がいつまでも生きているという保証はないのだ。
「だが、黒いアグモンにつながる確たる情報はなかった。いまに至るまで」
象潟は、もう情報提供には期待していないのだろう。
「見つかれば……もし失踪したパートナーデジモンが見つかれば、DMIAになった人間を助けることができるのか?」
エイジはたずねた。
龍泉寺教授の説明では――マインドリンク持続時間を超過、Lラインを超えてタイムアウトすると、人間の精神データがデジコアと癒着してしまうという。
それがどういう状態か、エイジは「ヤバイ」という感覚でしかわからなかったが……。
「DMIA患者は、意識が自我を認識できなくなっていると考えられる」
ドルモンが言った。
「えーと……」
エイジはちょっと理解が追い付かない。
「DMIAとなったデジモンもまた、ことごとく帰ってこないことからして、人間の精神データとデジコアとの癒着によって、パートナーデジモン自体にも深刻な不具合が生じてしまうようだ」
人間が意識不明になっただけなら、デジモンだけでも、知り合いのクラッカーなりハッカーなり、デジ対でもいい、連絡をよこすことくらいはできるのではないか。
だが、そうした例すら、知る限りはないという。
ましてやレオンとカヅチモンは〝乱渦〟に落ちてしまった。
〝壁〟のむこうの〝深層〟にだ。たとえ運よくロイヤルナイツから逃れられたとしても、自力での帰還は絶望的だろう。
「だが、希望はある」
象潟はデジモンリンカーでデータを出力した。
「お」
ルガモンが立ちあがって、データファイルに鼻先を寄せる。
「エサじゃないぞ、犬コロ」
ドルモンがあきれて言った。
ルガモンは……わりとエサでつられるのか。というか、こいつは狼だが、まったく番犬にはむいていない。
データがホロライズされた。
「注射器……?」
エイジは見たままをつぶやく。
「うわ!」
ルガモンは後ずさり壁を背にした。
「なんだ……おまえ、注射がこわいのか?」
エイジはぷっ、と笑った。
「う……うるせぇ! 嫌いなんだよ、その針!」
ルガモンは本気で嫌がっている。
「そういや、うちで飼っていた犬も注射嫌いだったなぁ」
「なんか、すまんな」
ルガモンのリアクションに象潟も困ってしまった。
いちいち話が脱線するので、じれたドルモンが早口で説明しはじめた。
「見てのとおりの注射器だ。こいつはDMIAの〝特効薬〟」
「特効薬……治療できるのか!?」
エイジは声を上げた。

この注射器のデータで植物状態のレオンを助けられる……?
「これは〝トニック〟……一種の医療用覚醒剤だ」
「え」
危険な言葉のひびきにエイジは困惑した。
ドラッグ、危険薬物を連想したからだ。
「デジコアに癒着してしまった人間の意識をひっぺがす。自分を自分と認識できるようにする」
「できるのか、そんなこと……」
「このトニックは、もともとマインドリンク持続時間を延長する目的で開発されたものだ」
「延長……マインドリンクを引き延ばすための?」
「気つけ薬さ」
「ああ、こういうのか」
エイジは飲んでいたエナジードリンクを手にした。
ようするに気合いと前借りで、ちょっとだけマインドリンク時間を延ばそうというわけだ。
「副作用の問題で実用化には至っていないけど……DMIA患者の、精神データのデジコアとの分離という治療用途に用いることができる可能性が出てきた。実験室レベルだけど、AIによるシミュレーションが行われて有望視されている」
試験用のデジモンと、人間を複写したパーソナルAIを用いて擬似的なDMIA患者を用意。トニックを投与したシミュレーションの結果、AIのデジコアからの分離に成功したという。
「じゃあ、そのトニックをレオンに打てば……」
「もちろんDDLの医療室のベッドにいるレオン・アレクサンダーにではなくて、デジタルワールドのどこかにいる彼のパートナーデジモンのデジコアに打つんだけどね」
ドルモンが言った。
液体が入った注射器のデータが、空中でゆっくりと回転する。
「そっか……それ、マーヴィンとかが開発したのか?」
「いいや。これは、とある研究室から提供されたものだ」
「提供? 研究室って……」
「D4だよ。龍泉寺研究室」
ドルモンの言葉に、エイジは驚いた。
DMIAの特効薬であるトニックがAE社のDDLで開発された。
龍泉寺教授がだ。
それ自体は、なにもおかしなことはない。むしろ、そんなもの開発できるのはDDLしかない。
引っかかるのは――
「なんでクラッカーのあんたらが、そんなものを?」
エイジはドルモンと象潟の話を信じかけている。
信じるからには、疑問はひとつも残しておきたくなかったのだ。
「われわれは龍泉寺教授と取引した」
ドルモンが言った。
「…………! どんな」
「われわれは龍泉寺にトニックの提供を受ける。龍泉寺はトニック投与の臨床データをすべて得る。交換条件だ」
話は通じる。
パーソナルAIによるシミュレーションではなく、実際にトニックを、法の外のデジタルワールドで法の外にいるクラッカーによって投与させる。
「象潟さんは、それでいいのか?」
もし黒いアグモンが見つかったとして……100%、DMIAになったかつての仲間が助かるという保証はないだろう。
下手をすれば仲間の命をかけた人体実験になってしまう。
象潟は……無言で仮想モニタに映像を出した。
天井からのアングル、監視カメラ風の映像だ。
医療施設。
そこらの病院にあるような設備ではなかった。カプセル状の装置のなかで、だれかが色のついた液体に浮かんでいる。不鮮明だが若い女性のようだ。
「彼女が、象潟さんの仲間……?」
「いまではこうして、ごくたまに送られてくる映像で確認するだけだ。彼女の肉体はかろうじて保たれてはいるが……それだけだ。トニック投与が成功したとして、この体に戻った彼女の意識がどうなるのか」
そもそも帰ってこられるのか。
いくらシミュレーションでは成功したといっても、実際どうなるかはわからない。
「このトニックは希望だ。希望だと私は考えた」
象潟は手のひらのなかで注射器のデータをにぎりしめる。
「象潟さん……あんた、龍泉寺教授を信頼しているんだな」
「きみは違うのか? エイジ」
逆にたずねられる。
「してるね」エイジは迷いなくこたえた。「そのトニックが〝D4〟だっていうなら、なんの疑問もない。お訪ね者のクラッカーなのに、こうしてリアルで訪ねてきたあんた……象潟さんを信じるし、龍泉寺教授を信頼している」
エイジにしてみれば、龍泉寺を信頼すればこそ、おなじように教授を信じている象潟講介という男の話を信じられた。
「では、今後も協力してもらえるだろうか、クラッカー・エイジ……そしてルガモン」
ドルモンは言質をも求めた。
「ああ……おまえもいいな、ルガモン」
「おう! 静電気野郎のおケツに、その針ブスッと刺してやるぜ」、
「下品だね、ルガモンは」
「うるせぇ……やんのか、こら」
「はいはい、話がややこしくなるから、そのへんにしとこうねー」
エイジは相棒をなだめた。
やっぱりルガモンは下に見られるのが大嫌いなのだった。これはもうデジコアに刻まれた狼のデータによる性分だろう。
「やれやれ」
「ドルモンも、そのへんにしといてねー……てゆーかさ! 象潟さんとドルモン、どっちがリーダーなのかわかんねぇ感じだな!」
エイジの勝手なイメージだが、スゴ腕クラッカーほどデジモンをツールとして、クールに使いこなすものだと思っていた。
むしろ、しゃべりはドルモンに任せているようでもある。
「ドルモンはSoCのリーダーだからな。ふたりで組織を率いている」
象潟が言った。
「へえ、そうだったんだ! リーダー・タルタロスってふたりのことだったんだな」
エイジは感心した。
「そう考えてもらって問題ない。ドルモンは……進化した彼はウォールスラムの街区をひとつ支配してもいる」
「あ? ドルモンが……」
ルガモンが反応する。
「9番街の魔狼のようにな。SoCにとっても、デジタルワールドにおける重要拠点だ」
ウォールスラムの一部を、人間のパートナーであるデジモンが支配していてもおかしくはないだろう。それほどリアルワールドとデジタルワールドはつながっている。
エイジは……話をまとめた。
「おれたちはレオンとパルスモンを、そっちは黒いアグモンを捜している。そのDMIAの治療薬――トニックって数はあるのか?」
「手持ちはこの1本だけだ」
ドルモンが答えた。
もちろんD4の最高機密というからには、データだからといってコピペで増やすなんてことはできなくなっている
「龍泉寺教授に頼んでみるか……レオンのためだし、なんとかしてくれるはず」
「いや……とにかくDMIAになったデジモンを捕獲できればいいんだ。ハッカー・ジャッジのパートナーデジモンを」
「あ、そっか」
いつものようにデジモンを捕獲して、ドックを龍泉寺教授のところに持ちこめばいい。そのうえで、より設備の整ったD4でトニックを投与してもらうのだ。
とにかく、レオンのデジモンの捜索と確保だ。
「じゃあ……いちばん肝心な話だ」
エイジは象潟とドルモンを見た。
「――伝説のリーダー・タルタロスが、やみくもに迷子捜しをしてきたわけじゃないはずだ。治療薬はある。あとは、どうやってDMIAになったデジモンを捜索するか」
「おお! エイジ、するどいな!」
ルガモンが珍しくエイジをほめた。
「それはね……」
言いかけたドルモンを制して、象潟は立ちあがった。
「近くに車をまわしてある。エイジ、出かける準備を。そのままでいい」
「え!? ここで急展開?」
エイジはそわそわした。
「ここは危険だ。もう、じきにデジ対が……警察がくる」
象潟はスマホでなにかを確認しつつ、言った。
「マジ……?」
驚いていると、アパートの外で車が停車した気配がした。
まさかパトカー……。
いいや、象潟がスマホで自分の車を呼んだらしい。ここ数年のあいだに電臨区では自動運転が普通になっている。
「私のセーフハウスに」
「おお、アジト!」
マンガかなにかで聞いたことがある。足がつかない安全な隠れ家だ。
ドルモンが玄関に歩く。象潟がそれに続く。
「あとは車のなかで話そう。SoCの最終計画……オペレーション〝タルタロス〟を再起動する」
「オペレーション・タルタロス……」
「なんだ、盛りあがるところか?」
エイジとルガモンは顔を見あわせた。
「エイジ……条件は提示した。くるのか、おりるのか……いま、ここで決めろ」
象潟は決断を促す。
「行くさ」
「この物語の先には……これまでおまえを守ってきたものは、なにもないぞ」
3畳の家も。わずかな貯金も。
法律も常識も。
ひとたびネットワークにダイブすれば、あるのは自分という精神データとパートナーデジモンのふたりだけだ。
デジタルワールドとリアルワールドの軛を外し、そして、超える。
「だとしても、後悔よりも怖いものはないってわかった」
エイジにわかったことは、いまはそれだけだ。
そして、
「――おれの心をえぐって支配しようとする、この喪失感……この心の穴。なにも……だれも埋めてはくれない。動かなきゃ……怖くても、わからなくても、やれることをやらなきゃ」
エイジの心の叫びに、まさに象潟は同志としてうなずいた。
「その後悔と喪失感を愛せ。不自由な自由を……それがクラッカーだ」
「うん……おれはクラッカーだから!」
ネットワークの自由。デジタルワールドの自由。
「心の穴だかなんだかよくわかんねーけど……エイジ。おれなんかいつも、デジコアにおまえの意識を居候させてんだぜ?」
「ルガモン……」
「てめーの心にも穴ぐらがあるっていうなら、こんど、おれが遊びにいってやるよ」
ルガモンの言葉に、エイジはそっとおでこのインターフェースに手を置く。
パートナーデジモンはだまって受けいれた。
「頼むぜ、相棒」
「おう」
ふたりの決意を確かめた象潟は、告げた。
「作戦目標はウォールゲートだ……〝深層〟デジタルワールドにクラッキングをしかける……!」
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo