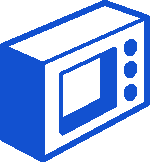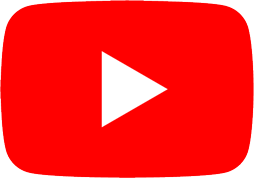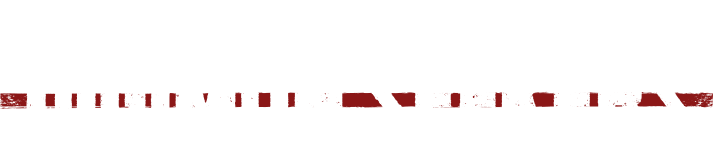-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER3
Unit 11:Digital Missing In Action
Chap.3-10
メシをかきこんでシャワーを浴びたエイジは、着替えて、やっとシャキっとした。
そのあいだ来客の男はルガモンの相手をしていた。
デジモンの扱いが手慣れている。
ホロライズしたデジモンと自然にコミュニケーションがとれることからして、この男は間違いなくクラッカー、ないしハッカー、とにかくデジタルワールドを知る側の人間だ。
「お待たせしま……えーっと、なんか、ちらかっててすいません」
エイジはタオルで髪をふきながら座った。
「気にするな。うちも似たようなものだ」
「はぁ」
「急に押しかけてすまない。いまさらだが」
男はくつろいだ感じで缶コーヒーを飲んでいる。
エイジをまったく警戒していない。実際、この部屋には武器になりそうなナイフや包丁すらないのだが。
「えーと……差し入れまでいただいて恐縮ですけど、ええと、どちら様です?」
「SoCのリーダー、タルタロスだ」
クラッカー・タルタロス……の中の人。さすがに本名は名乗らない。
「あ、エイジ……永住瑛士です」
確かにタルタロスからショートメッセージが届いたタイミングで、この男は現れたのだが。
「ああ、私がSoCのリーダーであるという証拠かな」
「できれば」
「ネットワークの住人が、自分が自分であることを証明するのはむずかしい。これでいいか……ドルモン」
ホロライズ。
男が腕につけたデジモンリンカーから現れたのは、
「あ! ウォールスラムで会ったボロ布野郎!」
ルガモンが声を上げた。
ホロライズしたのはボロ布をまとったデジモン。SoCの入隊試験のとき、ウォールスラムのビルの屋上で会ってマッピングの仕事をふってきた相手だ。
デジモンがボロ布を脱ぐ。
ふさふさの尻尾、背中には小さな翼。ルガモンとおなじくらいのサイズの成長期デジモンだ。
「ボロ布じゃない、おれはドルモン」
「私の友人、パートナーデジモンだ」
男が紹介した。
人間がふたり、デジモンが2体もいると3畳間はぎゅうぎゅうだ。
「え……ちょ、待って? あのときの……面接官の人!」
エイジはつい相手を指さしてしまった。
「きみらが最初に会ったSoCの面接官はタルタロスのサブのアバターだ」
ドルモンが答えた。

SoCの面接官はリーダー・タルタロスその人だった。
あの入隊試験のことを知っているのは、限られた者だけのはず。
少なくとも、この男がSoCの重要関係者であることはわかった。いまはそれで充分だろう。
「――なんで」
「ん?」
「伝説のクラッカー・タルタロスが、なんでおれなんかの面接を……考えられる理由はひとつだ。あんたは、おれがSoCに入隊しようとした理由を知っていた」
エイジは考えた。
龍泉寺教授という特別な依頼主の存在を知っていたからだ、としか考えられない。
「なるほど……マーヴィンが言ってたように、すっとぼけているようで肝心なことは見逃さないんだな」
ドルモンは少しだけ感心した。
「…………。え?」
エイジはドルモンを見た。
「そのとおり。おれたちは、きみらが龍泉寺教授のスパイとして、われわれSoCを調査しようとしていたことを知っていた」
「わかっていて、おれとルガモンをSoCに入れたのは……?」
目の前で缶コーヒーを飲んでいる男とではなく、デジモンと話していることにとまどいながら、エイジはたずねた。
「ひとつは、きみらが戦力になるからだ。実際、きみらはX国データサーバにおいてマーヴィンの命を救ってくれた。ありがとう、あらためて感謝する」
「あ、ども」
「失礼なやつだけど、肝心なところは礼儀正しいんだな、おまえ」
ルガモンはドルモンを見なおした。
「つまり……きみらが龍泉寺教授がよこしたスパイであればこそ、われわれはナガスミ・エイジというクラッカーを信用できたのさ」
あの龍泉寺教授が雇用したクラッカーがヘボであるわけがない、という理屈だ。
「すげーな教授! クラックチームやデジモンにも尊敬されてるのか」
だからエイジは、たいした実績もない新人なのに、SoCの幹部たちから一定のリスペクトを受けていた。
「そしてもうひとつ……こちらが真の理由だ」
「それを聞きたい。ドルモン……SoCは究極体デジモンを収集して、なにをやらかすつもりなんだ」
エイジは差し入れのエナジードリンクをゴクゴク飲んだ。
吐き気はどこかにいってしまった。ふしぎなものでデジモンリンカーのバイタルサインも正常値に戻っている。
――これは私の〝物語〟なんだ。
男がつぶやいた言葉にエイジはとまどった。
「…………?」
「たとえ話さ」
「クラッカー・タルタロスの物語ということだね」ドルモンがフォローした。「その物語にきみらを……エイジとルガモンを巻きこんだ。もちろんおれ自身もだけど」
「ようするに……〝すべてはSoCのシナリオどおり〟ってことか?」
エイジは端的に理解した。
「そこまでは言っていない。登場人物は、演じることはできても物語の結末を決めることはできないからね」
ドルモンは思わせぶりに答えた。
エイジは……やっと、少しだけわかった。
いいや話はさっぱりわからないのだが、エイジのドルモンに対する違和感は――このドルモンは自分の意思を持っている。
いや、もちろんデジモンはただのAIではなく、パーソナリティがあり、意思があるのだが。
クラッカー・タルタロスのパートナーデジモンだから、というだけではない。
なんというのだ……主体性?
ドルモンにはドルモンの目的があって……?
でなくては人間様を差しおいて、これほど自分が前に出て話をしないだろう。
「なんだそりゃ……? おれは、おれがやりたいようにしかやってねぇぞ!」
すべてわれわれのシナリオどおり――とかいう展開が、ルガモンはなんとなく気にいらないらしい。
「きみはそういうやつらしいね、ルガモン」
「おれとエイジはな! パルスモンとレオンを助けるんだ!」
理由は単純明快だったが、ルガモンにも自分の目的と意思がある。
「――そこにタルタロスのおっさんが来た。クラックチームでSoCのリーダーだ。だから、おまえらをこの家に入れた」
ルガモンはパルスモンを助けるために、SoCのリーダーのチカラを借りるつもりだった。
そもそもマインドリンクは人類が開発した技術だ。デジタルワールドに詳しい専門家の知見がいる。
エイジは、あらためて自分たちの目的を明らかにした。
「おれとルガモンは、DMIAになったレオン・アレクサンダーと、そのパートナーデジモン、パルスモンを助けたい。そのために、どうすればいいのかを知りたい」
「ハッカー・ジャッジへの報復をきみに依頼したのは、われわれSoCだけど」
ドルモンが言った。
X国データサーバの作戦において、ハッカー・ジャッジの横槍によって国家機密級デジモン・ムゲンドラモンを喪失したことに対する報復として……というのが大義名分だった。
「――だれかのせいにするのは簡単だ。でもヘマをして、レオンをDMIAにしてしまったのはおれなんだ」
報復の手段はエイジに一任されていたのだ。
「せっかく完全体になったのに、おれが暴走しちまった」
ルガモンは悔しそうだ。
「では」ドルモンが言った。「われわれは、引き続き目的をともにしているということだな」
「…………? おなじ目的?」
このふたりは……エイジは感じた。
男とドルモンは、クラッカーとパートナーデジモンというだけではない、もっと違った関係なのではないか、と。
「SoCの真の目的もまた、そこにあるということだ。DMIAとなった人間の救出。そのためにタルタロスはチームを立ちあげた」
エイジにとっては意外だった。
クラックチームというのは……経済的な利益の追求、もしくは思想のようなものをかかげて結成されるのだと思っていた。
「ネットワークの自由とかデジタルワールドの自由とか、そういうのじゃないの?」
「それはクラックチームの理念だろう。本来SoCは、もっと小さな集まりだった。マーヴィンをはじめ、限られた幹部だけが目的を共有してくれている。われわれは人間とデジモンという〝系〟の異なる生命体だが、たがいを理解し、目的の達成という点で一致した」
ドルモンが言った。ゆえにわれわれは同志だ、と。
エイジは男に視線をやった。
「さっき、あんたが言ったことが気になる。リーダー・タルタロスは作戦をともにした仲間をけっしてDMIAにしないって聞いたけど?」
――私も、そうだったからだ。
――大切な人を、自分のせいでDMIAにしてしまった。
「そういう評判だね。でも、それは……」
「それは誤解だ。いや、買いかぶりだな」
ドルモンが言いかけたところで、男が言葉を重ねる。
「…………」
「私は、そもそも最初に大切な人をデジタルワールドで失ってしまった男だ。だから二度と過ちをおかさないために、そうした評判が立つほど慎重になった面はあるだろう」
「聞かせくれ」
エイジは言った。
「…………」
「話せることだけでいい」
エイジは男を量る。
リーダー・タルタロスは応じる。
初めからそのつもりだったのだろう。でなくてはエイジの家に、自ら現れるわけもない。
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo