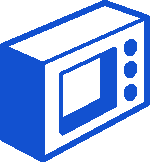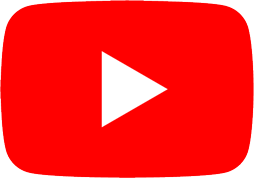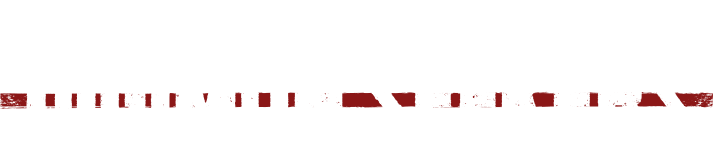-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER2
Hacker Leon:WWW Airlines flight626
Chap.2-3
チャンネルSoC、マーヴィンの部屋。
『∞』作戦に参加するSoCの幹部メンバーが集まっていた。
エイジをふくめて8人。みな、当然だがアバターの姿だ。デジモンは連れていない。
仮想モニタに作戦のブリーフィング画面が表示された。
「外国なんだ……」
エイジはつい素のリアクションで、ごくっとつばをのんだ。
デジタルワールドに国境はない。
でも人間のネットワークには国境があるのだ。サーバは物理的に、いずれかの国家、組織に属している。
うわさされたSoCの〝大規模な活動〟とは、とある国家のサーバへの侵入だった。
某X国。
「GDPでは最貧国のカテゴリだが、札つきのテロ支援国家だ」
マーヴィンが言った。
なんとかという独裁者が何十年と支配を続けている国だ。
「X国……ニュースとかでは聞くけどさ」
「エイジ?」
マーヴィンと、ほかの幹部メンバーも、この新人の素人っぽいリアクションにとまどっている。
「なにが気にいらなくてやっちゃうわけ? X国」
エイジの質問に、SoCの幹部たちは、
――HAHAHAHA!
爆笑した。
たぶんだが……幹部の大半は日本人ではないのだろう。エイジは思った。
「すまない、クラッカー・エイジ。スゴ腕のきみにはたいくつな説明ばかりだろうが、順をおってすすめさせてくれ。おなじSoCのメンバーとはいっても、これだけの幹部級がチームを組むことは、めったにないんだ」
マーヴィンはていねいに話した。
X国は、ある時期は核開発、そして最近ではデジタルワールドがらみのサイバー戦争を盾に、水面下で国際社会をおどすテロ外交を続けている。
「近年、X国によってネットワーク犯罪が多発している。先日も取引所が攻撃されて、数億ドル相当の暗号通貨が盗みだされた」
「あの事件か……!」
エイジでも知っている。
「そうだ、X国によるデジモン犯罪だった。こうしたテロリズムは、まわりまわってわれわれのGriMM経済圏を揺るがしかねない。クラックチームの理念と自由をだ」
GriMMのマーケットは、独自の暗号通貨DCによってまわっている。
米ドルに代表される法定通貨から独立することで、GriMMは独自の経済圏をなしえた。それこそがSoCの活動の資金源でもある。
裏をかえせば……。
無法のデジタルワールドをベースとするGriMM経済圏は、リアルの市場経済を揺るがしている。通貨発行権の独占によって国益を求めてきた各国中央銀行と政府にとって、GriMMは存在そのものが危険なのだ。
もし、デジタルワールドがリアルワールドと同等の価値を有するなら……?
暗号通貨DCは、ドルと同等の価値を有することになる。そうなれば、あらゆる主要通貨の価値を相対的に下落、毀損させる。
どうなるか。
デジタルワールドの存在すら知らされていない大多数の一般人は大損をして、すでにデジタルワールドに利権を築いている者が、あらたな、きわめて有力な支配者層になるだろう。
過去にも繰りかえされた、それ以上の、とてつもない金融パニックを引き起こすはずだ。
だから既存の首脳層は、デジタルワールドを規制し、ひそかに自分たちで管理しようと躍起なのだ。
(…………)
正直エイジにはちょっとむずかしい話だったが……各国政府とクラックチームが対立する理由が、デジタルワールドの利権だというのはわかる。
デジタルワールドは金になるのだ。
それこそ、エイジがクラッカーになった理由なのだから。
国際社会はクラックチームを危険視してテロリスト呼ばわりするし、クラッカーたちは、自分たちがリスクを犯して開拓してきたフロンティアであるデジタルワールドに自由を主張する。
「X国がサイバーテロ、デジモン犯罪をやらかしてるとして……それって広い意味では、おれたちクラッカーの同類ってことだよね」
エイジが言うと、また幹部たちが笑った。
まったく、クラッカーというのは正義の味方でもなんでもない。
「そうだなエイジ。違うとすれば、X国の独裁者様にはネットワークの自由、デジタルワールドの自由という理念はない。あるとすれば私利私欲だけだ」
「おれも似たようなもんだけど。デジタルワールドでひと山あてたい。みんな人生を変えたくてクラッカーをやってるんじゃ?」
「ああ、そうだな。おれたちがX国をやる理由は……」
――ムカつくからだよ、あの独裁者が。
幹部たちは言葉を飾らない。
「おれたちSoCにとって、あのうすらハゲ――X国は許しがたいんだ。なにしろ……」
「究極体〝ムゲンドラモン〟」
と、エイジが言った。
「…………!」
「X国は、彼らの究極体デジモンを用いたデジモン犯罪とサイバーテロを、ぜんぶSoCの仕業にしているからだ」
昨日――
エイジはマーヴィンと面会したあと、報告がてら龍泉寺教授とチャットで話していた。
――『∞作戦』……そうか、SoCのねらいはX国か。
オペレーション・インフィニティ。
その作戦名だけで、龍泉寺はすぐに見抜いた。
X国と独裁者のこと。究極体ムゲンドラモンを所有しているのはX国だけであること。そしてSoCとX国との浅からぬ因縁……さまざまな情報を、あらかじめエイジに教えてくれたのだ。
エイジがすべて言ってしまったので、マーヴィンは息をついた。
「そこまで知っていたか」
デジモン犯罪は、事件事故そのもののこと以外は、おおっぴらなニュースにはならない。デジタルワールドとデジモンの存在は、一般にはふせられているからだ。
「ふざけた独裁者には、オトシマエをつけなくちゃならないと」
「そうだ。この業界はナメられたら負けだ……!」
マーヴィンは言いはなった。
マフィアの、ヤクザの論理。ナメられたらやりかえす。クラッカーとはそういう稼業だ。
――全員、そろったな。
ボイスチャットに声が飛んだ。
その場にいた全員に緊張がはしった。それがアバター越しにでもわかった。
『新人もいるから最初にあいさつしておく。SoCのリーダー・タルタロスだ。この作戦の指揮を執る』
その言葉にエイジは息をのんだ。
(リーダー・タルタロス……!)
ついに、ご対面だ。声だけだが。
『作戦目標はX国データサーバ。目標は、その無力化および国家機密級デジモン・ムゲンドラモンの捕獲だ』
国家機密級デジモン。
つまりは国家レベルのセキュリティを打ち破ることができる、強力なデジモンのことだ。裏を返せば、外部からの攻撃に対して強固なセキュリティを構築できるデジモンでもある。
まさにサイバー戦争、ハイブリッド戦争における切り札ともなる存在。
機密級デジモンを所有している国家は、たとえ小国であっても、国際社会にとって無視できない存在になり得る。かつての核兵器のように。
『作戦の最大の目的は、あのうすらハゲの鼻を明かすことだ』
このリーダー・タルタロスの言葉に、参加メンバーが盛りあがる。
ツールの時計を、現地時間に合わせる。
『この戦いは自由の戦い。自由の旗をかかげる者は、無法の戦いに挑むしかない』
「ネットワークの自由を!」
リーダーの言葉に、マーヴィンが応じ、メンバーたちが声を返す。
――デジタルワールドの自由を!
この団結力こそが武闘派クラックチーム・サンズオブケイオスだ。
もし、この作戦が成功すれば。
国際社会は、いよいよSoCを無視できなくなる。国家を凌駕するほどのクラックチームとして。
リーダー・タルタロスの存在感を、エイジは強く感じた。
幹部たちが、それぞれのデジモンを出す。
クラッカー好みのサイボーグ系デジモンが多いようだ。
エイジはいったんマイクを切って、腕のデジモンリンカーを見た。
「おれたちも行くぞ、ルガモン! えいえいおー」
「作戦ファイルに目をとおせよ。おれは、もうぜんぶ読んだ」
「あー」
仮想モニタのなかで、参加メンバーたちのアバターが消えていく。
続いてデジモンたちが、マーヴィンの部屋からどこかに転送されていった。
マインドリンクしたのだ。
エイジは共有されたファイルから、つぎの作戦ポイントの座標を読みだした。
「デジタルワールドを経由して、一気にX国データサーバにダイレクトアタック……か。なるほどね」
めちゃくちゃ、どきどきする。
どんな強固なセキュリティを築いても、これをやられるとニンジャみたいに容易に侵入を許してしまう。
エイジはデジモンリンカーのメニューを選択した。
〝軛〟をこえる――
「いいぞ……こい、エイジ」
「行こうぜ、相棒! 超一流の、その、むこう側に!」
この作戦を成功させれば、いよいよリーダー・タルタロスと対面できる気がする。
深呼吸。
センサーが生体情報を計測、バイタルチェックのあとコマンドを許可した。
限定解除。
エイジの意識は光になって解き放たれた。
――〝マインドリンク〟!

マインドリンクによって、エイジの精神はデジタルデータに変換、その意識はルガモンのデジコアと一体化した。
「幽体離脱~」
「なんだそれ」
エイジがふざけると、ルガモンが反応する。
「マインドリンクって、おれが生き霊になっておまえにとり憑いてるとか、そんな感じがしない?」
「生き霊とか憑くとか、わかんねーよ……! なら、いまリアルのおまえはどうなってんだエイジ? 死んでるのか」
「いや……生きてるだろ、そこは!」
「ほんとうに?」
「そういわれると自信が……そういや、どうなってんだろうな? おれの体……」
エイジはなんだか不安になってきた。
「こないだリューセンジに説明されただろ? マインドリンクのリスクについて」
ルガモンがあきれる。
「あー……うん、龍泉寺教授の話、基本、むずかしいから。マインドリンクするときは人目につかないところで、念のためトイレにいっておけとは言われたな」
意識を失って、眠っているような状態なのだろうか。
「帰ったとき、漏らしてたら笑っていいか」
「トイレに座ったままのほうがよかったかな?」
「痔になるぞ」
「SoCの幹部連中は、どうしてるんだろうなー」
話しながら、エイジは先日、龍泉寺に説明されたマインドリンクのリスクについて思いかえした。

――SoCの幹部と接触する前に、あらためて大切なことを伝えよう。今後、きみの生命にかかわる重要なことだ。
DDLのオフィスで、龍泉寺はモニタに機密ファイルをひらいた。
――『禁D4 第■■■回ML実験 ■■■■年■■月■■日 於DDL』

黒塗りのタイトル画面のあと、記録映像が流れる。
MLは、マインドリンクの略。
DDLのD4区画において、某日行われたマインドリンク実験ということだ。
実験室を、天井から撮影したヒキの映像になる。
ヘルメット状の計測機器を頭からかぶった、コードがつながれた特殊なスーツで身をつつんだ人物がシートに腰かけている。
彼――彼女?
スーツのせいで性別もわからないが、被験者でありマインドリンカーだ。
「この人は……?」
「ラボに所属するハッカーだ」龍泉寺がエイジに答えた。「優秀だったよ。マインドリンク持続時間は、当時、うちに所属するハッカーでもっとも長かった。シミュレーションテストの記録は、確か、未だに破られていないはずだ」
映像は倍速、早回しだ。
なんの目的で、どんなデジモンとマインドリンクしていたのだろう。
そのことをエイジがたずねる前に、異変は起きた。
――…………!
音声がOFFだったので、なにを言っているのかはわからない。
だが突然、シートに横たわったハッカーがビクンと痙攣した。
エイジはびくっとした。
電気ショックを受けたように、ハッカーがはげしくのたうつ。シートベルトで体を固定していなければ、シートから転がり落ちてしまったはずだ。
あわてて駆けよったスタッフたちが画面に現れる。
ハッカーを押さえる。聞こえない声と悲鳴が飛びかった。
……………………。
ややあってハッカーは静かに、動かなくなった。
スタッフが手当てにあたる。スーツからコードを外して、ヘルメットを脱がそうとしたところで映像はとぎれた。
「――いまのハッカーは……?」
息をのみながら、エイジは龍泉寺にたずねた。
「パートナーのデジモンにトラブルがあった。結論を言えば、そのためにマインドリンクのリミットをオーバーしてしまった」
「マインドリンクのリミット……?」
「デジモンリンカーのマニュアルは読んでいないのかな?」
龍泉寺は肩をすくめる。
「あー……使いながら覚えるタイプで……」
「言うまでもなくマインドリンクには重大なリスクがある」
龍泉寺の言葉に、エイジは生返事でうなずいた。
「リスク……?」
「マインドリンクによってデジコアと一体化した結果、デジモンとの通信速度、コマンド処理速度は段違いに上がる。異次元ともいうべきレベルだ。だが、マインドリンクにはタイムリミットがある」
「タイムリミット」
「マインドリンクが可能な時間だ。この長さはハッカー、クラッカー個人の素質と訓練、そしてパートナーとなるデジモンとの相性と、その進化段階によって決まる」
「進化段階」
「ルガモンのように成長期ならカウントダウンはゆるやかで、長時間ウォールスラムに滞在できたはずだ。だが、これが成熟期、さらに進化がすすめば急速にカウントがすすむことになる」
「…………。もし、なにかの間違いで究極体に進化しちゃったりしたら……?」
「究極体ともなれば、マインドリンク状態で、まともに活動できる時間は限られるだろう」
龍泉寺の言葉に、エイジは息をのんだ。
「なんで……制限時間なんてあるんですか?」
「接続限界値――それ以上マインドリンクを継続できない限界を、私はLラインと名づけた。リミットだ。これを超えると、精神データがデジコアと癒着したまま、あちらがわ……デジタルワールドに意識だけが取り残されることになりかねない」
「意識が……癒着?」
「デジモンのデジコアにも過剰な負荷がかかり、最悪デジコアを破損する。少なくともデータ領域にエラーを生じてしまうだろう」
「制限時間……Lラインを超えると、さっきの映像のハッカーの人は、どうなっちゃったんですか?」
――DMIA。
龍泉寺はアルファベット4文字を口にした。
なにかの略語だ。
「DMIA……?」
「DMIA(Digital Missing In Action)……デジタルワールド行動中失踪、行方不明という。すなわちロストだ。あのハッカーの意識は、リアルワールドと肉体に帰ってこられなくなったまま行方知れずになった」
「…………!」
エイジはショックを受けた。
まさか……デジタルワールドにもぐったまま、浮かんでこられなくなったのか。
「あの……ええと、そうだ、肉体は? だって肉体ごとデジタルワールドに行けるわけじゃないでしょ?」
「肉体は実験室に残されたよ。意識の抜け殻としてね」
龍泉寺の言葉は、あのハッカーの不吉な運命をしめしていた。
「抜け殻って……まさか」
「人生を退場することになった」
いわゆる植物状態になったという。それも回復することのない。
「…………!」
「DMIAは近年増加している。市井のクラッカーたちの能力と技術は目覚ましく向上して、マインドリンクを実行する者も増えているからだ。それに対応する警察とデジ対にも。いずれにせよ、トラブルが起きてLラインをオーバーした場合、結末はふたとおり」
「ふたとおり……」
「ひとつは、だれにも発見されないまま、肉体が死に至る。クラッカーはこれが非常に多い。エイジくん……もし、きみがDMIAになったら、そうなってしまうのではないかな」
「あ……そうか」
3畳ワンルームのロフトで、だれにも知られず死ぬことになる。
家賃は自動振込だ。貯金が増えたから何ヶ月たっても払えるし、腐って隣家に悪臭が漏れるまで放置されるかもしれない。
そして原因不明の孤独死として処理される……。
「もうひとつは、運よく意識不明者として発見されて適切に処置される。いわゆる植物状態のまま肉体は保たれる。だが……多くの場合は、それも長くは続かない。最悪なことは……DMIAと判定されてから意識を自然回復し、リアルワールドに元どおり復帰できた者は、私が知る限りはひとりもいないことだ」
「ひとりも……!?」
「なにしろロストしたパートナーデジモンも見つからない。どこかにいってしまう。見つかったとしても、精神データはデジコアと癒着してしまっているはずだ」
話の内容がショックすぎて、エイジは言葉をなくしてしまった。
もちろんタイムリミットさえ守れば、マインドリンクは最高のパフォーマンスを発揮するだろうが……。
「安全管理のために、私はLラインのほかにKラインを設定した」
「K……」
「危険、警告だ。警告基準値であるKラインは、そこでデジタルワールドを離脱してマインドリンクを解除すれば、安全に意識がリアルワールドに戻れるだろう目安だ」
――Lライン(接続限界値)とKライン(警告基準値)。
「それらは警察でも採用されて、厳密に運用されている。デジ対は引き際がはやいと思うことがあるかもしれないが、そのためだよ」――――
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo