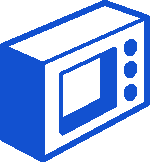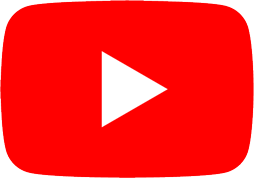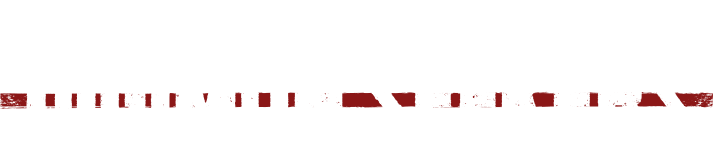-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER2
Hacker Leon:WWW Airlines flight626
Chap.2-1
WWW-626便。
その航空会社のレターコード、便名と機種まで覚えている人間は、多くはないはずだ。日々、膨大なニュースが駆けめぐる現代社会。悲劇的な航空機事故は、たびたびではないが、毎年のように世界のどこかで起きている。
死者・行方不明者***名。
離陸後、高度3万数千フィートを順調に飛行中だったWWW航空の機体は、突如として、不可解な挙動をとったあと予定されたルートを大きく外れ、行方不明となった。
海に落ちたことは確実だったが、機体とフライトレコーダーは未発見のままだ。
遺体はひとつも揚がっていない。乗客乗員の全員が死亡したとされて、いまに至る。数ヶ月後、はるか数千キロ離れた場所に626便の残骸の一部が漂着したという。
原因は不明。
事故なのか事件なのかさえ。機体トラブル、パイロットの精神錯乱などさまざまな可能性が指摘されたが、どれも確証はなかった。
ただ、この謎につつまれた航空機事故の真実を知る者はいた。
WWW航空626便の墜落は、デジモンと呼ばれるAIプログラムを用いた、クラッカーによるテロ行為だった。
そのことは公にはなっていない。
理解されないからだ。世界の大半の人々は、未だにデジモンとデジタルワールドの存在さえ知らずにいた。

「…………! はっ!」
はげしく息をついて、ベッドからはね起きた。
悪夢。
じっと身をかがめたまま呼吸を整える。暗闇のなかで手を伸ばす。
と、明かりがついた。
「うなされていたよ。だいじょうぶ、レオン?」
枕元にデジモンがいた。
ホロライズだ。照明ではなくデジモンが光っていた。そいつは電気をまとっていて、時折、小さな火花をちらしている。
――パルスモン 成長期 獣人型 ワクチン種
まるで電気の小妖精。
ジグザグに整えたイナズマスタイルの前髪がぴょこっと動いて、パートナーを心配する。
「また、あの事故の夢? 最近は見なくなってたのにね」
「そうだねパルスモン。あの事件の夢だ」
パルスモンの明かりをたよりに、ベッドサイドに置いたミネラルウォーターのボトルを手にして、キャップをあけて口にする。
飲みほした。
「薬はいるの?」
「だいじょうぶ、ありがとうパルスモン……もう、こんな時間か」
窓の外は、夜明け前の電臨区。
タワーマンションから見おろす夜景だ。
「今日は1限から授業でしょ? もうすこし寝たら」
「いや、もう起きるよ。つまんない教養科目だけど出席はきびしいから」
オンライン配信で講義を受ければいいのだが、出席チェックと、最後に小テストみたいなクイズがあるのでめんどうくさい。
「卒業しなくてもいいんじゃ? レオンはもう半分、アバディンエレクトロニクスの……DDLの社員みたいなものなんだし」
「ぼくは大学を卒業して、きちんと就職したいんだ。それが父さんとの約束だ。それにね……暇な大学生じゃなければやれないことはある」
「正義のハッカーとか?」
パルスモンは茶目っ気たっぷりにウィンクした。
「ははっ……シャワーを浴びたいな」
悪夢のせいで寝汗をかいていた。
レオン・アレクサンダーはけだるそうに立ちあがるとバスルームに歩いた。

デジタルワールド・ウォールスラム9番街。
九狼城の廟の前に、この界隈のボス――ルガモンと、ホロライズしたエイジの姿があった。
「――つまり、おまえ、記憶が戻ったわけじゃないってことか」
エイジはルガモンに言った。
「おれが、このウォールスラムの9番街で育って、ここらへんをナワバリにしていたことは臭いでわかるんだがな……」
記憶は断片的で、細かいことはさっぱりだと。
「そっかぁ……思いだせるといいな」
「いや、別に」
「え? そうなの」
ルガモンは自分の記憶がないことについて、たいしてこだわりがなさそうだ。
「おまえら人間は……昔のことぜんぶ覚えていて、いつまでも思いだしたいのか?」
「あー……小学校より前のことはぜんぜんだな。中高だって、別に思いだしたいこともないか」
高校卒業と同時にフリーター――クラッカーになったエイジは、必然的に、進学した者ばかりの友人関係をリセットしてしまったから。
「だろ。どうせ忘れるんだよ、どうでもいいことは」
「ルガモンって、なんかオトナだな。ハードボイルドってやつ?」
と、そのとき九狼城の広場にティラノモンが3体、あちこちの路地から現れた。
「おう、おまえら、おつかれ」
――ゴロゴロ……キュルキュルッ
ティラノモンたちはのどを鳴らすと、集めてきたデータをルガモンに渡した。
マッピングツールだ。データを集めさせて、同時に9番街にいるデジモンたちのおおまかな数も把握した。
「すっかりおまえの子分だな、ティラノモンたち……」
舎弟ってやつだ。
エイジはティラノモンたちにエサ肉を投げて与える。
「おまえも子分にしてやっていいぞ。いまなら4番目だ」
「おれはティラノモンのつぎかよ」
エイジは苦笑い。
「こいつらを定期的に9番街で巡回させておけ。パトロールだ。おれの留守中にナワバリに手を出そうとする、どあほうがいるかもしれないからな」
「ルーチンで予定を組んでおくか……頼むぞティラノモンズ」
エイジは自分よりも大きなティラノモンたちをなでた。
3頭のティラノモンは、ガウッ、とこたえる。
マインドリンクしたことがないので彼らとは話せないのだが……前とは違って、ティラノモンたちがなにかを伝えているのはわかった。
嫌がってはいない。
ウゥウウウウウウウウウウウッ…………!
ふいに、サイレンが鳴りひびいた。
「なんだ?」
エイジはキョロキョロした。デジモンリンカー、ツールの警告音ではない。
広場にいたデジモンたちが、あわてふためきながら逃げていく。みな建物のなかへ、地下室に下りていくデジモンもいた。
「エイジ」ルガモンが声を上げた。「戻れ……ティラノモンたちも回収だ」
「? なんで」
応えながら、エイジは仮想モニタを操作してティラノモンたちをドックに戻すと、自分もホロライズを解除、ルガモンのデジコアに戻った。
ルガモンの視野が、そのままエイジの目となる。
ヘッドアップの位置に仮想モニタが展開した。
ルガモンが九狼城のビルを駆けあがった。
ネットワークの海をあおぐ魔窟の最上階。そこに櫓(やぐら)が組まれていた。サイレンを鳴らしているのは見張りをしていたデジモンだ。
――〝乱渦(タービュランス)〟だ!
見張りのデジモンが叫んだ。
「タービュランス……?」
エイジには、なんのことかわからない。
でも、デジモンたちのあわてぶりから、大変なことが起きているのはわかった。
「…………! あれだ」
ルガモンが視線でしめす先には――
それは、まるで水面に生じた〝穴〟だった。
エイジが連想したのは、バスタブの栓を抜いたときに出きる渦だ。
ただ、スケールがでかい。
ざっと直径数十メートルはあるだろうか。ウォールスラムの外、なにもないノイズデータの〝砂海〟に発生した乾いた渦は、希薄なデータの塵を巻きこみながら、ゆっくりと移動していた。
「デジタルワールドを、リアルワールドのデータ汚染から守るためのセキュリティウォール……だが、それも完全じゃない。セキュリティには、かならずほころびがある。それが、あの〝乱渦〟だ」
ルガモンが語った。
セキュリティウォールはデジタルワールドを守る〝壁〟だ。
ウォールゲートは、トラフィックを管理する情報の〝門〟。
ウォールスラムは、そのウォールゲート周辺に吹きだまったジャンクデータの寄せ集めからなる。
ところが、デジタルワールドのシステムに管理されたゲート以外にも、文字どおりセキュリティの〝穴〟が生じることがある。
「つまり、あれはデジタルワールドのセキュリティの〝穴〟なのか!」
エイジはおおざっぱに理解した。
「そんなところだ。いつ、どこで発生するかわからない災害みたいなもの。ただ、あのへんは〝乱渦〟の巣でな……」
ルガモンは〝乱渦〟のゆくえを見定める。
「巣?」
「ウォールスラムからあふれたデータは鉄錆海岸から外界にはきだされている。海に流出した大量のゴミってところか……それが、なんの流れなのか、あのあたりで集まってゴミの浮島みたいになっている」
「ひどいもんだな……」
「あそこには〝ダストキングダム〟――ジャンクあさりの5番街のデジモンたちさえ寄りつかない。なんの役にも立たないノイズデータだからな。そのせいなのかどうか、あのあたりは〝歪む〟んだ」
「歪む……?」
「いろいろとだ。そして、歪みから〝乱渦〟が発生する。たいていはすぐ消えるんだが、たまにでかいのができる。ごくまれに、そいつがスラムを直撃すると……」
「どうなるんだ……?」
眼前の〝乱渦〟はウォールスラムのへりをかすめていく。
ゴゴゴゴゴゴゴゴッ…………!
そこらへんのスラムの外縁部が、データごと分解されながら〝乱渦〟に吸いこまれていったのが見えた。
「――街区のひとつくらい消滅することになる。住んでいるデジモンごとだ」
「…………! まじか」
さいわい今回の〝乱渦〟はウォールスラムをかすめたあと、遠ざかって、すぐに消失した。
サイレンが鳴り止む。
見おろすと、九狼城の広場に、またデジモンたちが姿を見せはじめた。
「いまの渦に吸いこまれると、どうなるんだ? あれがセキュリティの穴だっていうなら、もしかして……〝深層〟のデジタルワールドにつながっている?」
エイジは考えた。
セキュリティの穴の先は、当然、セキュリティウォールの向こう側ということだ。
「そもそも、おれたちデジモンは〝壁〟の向こうを〝深層〟なんて言い方はしないが。まぁ、どっちにしたってそりゃむりだ」
ルガモンは首を振った。
「なんで?」
「セキュリティの穴を放置しておくほど、デジタルワールドはのどかじゃない。もし人間が〝乱渦〟を利用して、おまえたちのいう〝深層〟のデジタルワールドを目指そうなんてしたら……」
「どうなるんだ……?」
エイジはつばをのんだ。
「たとえ〝乱渦〟そのものに耐えられたとしても、生きては通れない。奇蹟を起こしても不可能だ。デジタルワールドのシステム管理者は、リアルワールドからの侵入者をほうっておかないからだ……行くぞ」
ルガモンは、そこで話を切った。
「どこに?」
「どこに、じゃねーよ。リマインダーを設定したのはおまえだ。おれは親切に伝えてやっただけだ」
ルガモンに言われて、エイジは思いだした。
マインドリンクをしていると、ついつい時間の経過を忘れてしまう。
「あ! 龍泉寺教授と約束の時間だった!」
エイジはマインドリンクを切って、リアルワールドに帰還することにした。

アバディンエレクトロニクス社・電臨区デジタルラボ(DDL)。
「――おはよう、ふたりとも。実にすばらしい成果だ!」
オフィスで迎えた龍泉寺は、エイジとルガモンを祝福した。
「ありがとうございます! おれとルガモンがマインドリンクに成功したのは、デジモンリンカーと龍泉寺教授のおかげです!」
エイジは顔をほころばせた。
ルガモンはホロライズした姿で、ソファでまるくなる。
「どんなデジモンでも、高性能なガジェットがあればマインドリンクできるわけじゃない。ものごとには相性というものがある」
きみたちふたりの相性がよかったのさ、と龍泉寺は笑った。
「――マインドリンクを解除して、こっち……リアルで意識が戻ったときとか、ちょっと、めまいがするんですよね」
エイジは龍泉寺に相談した。
最初にマインドリンクから目覚めたとき、エイジは、自宅のロフトで壁にもたれた姿勢のままだった。そのときは船酔いみたいに頭がぐらんぐらんして吐きそうになったのだが。
「きみの生体データは、デジモンリンカーを通じてチェックされている。データを確認したが、異常は検知されなかったよ。過去の例からも……休んで回復したのであれば心配はいらない」
じき、慣れるはず。無重力空間から帰ってきたばかりの宇宙飛行士のようなものだ、と。
「よかった! あと、ルガモンなんですけど……なあ、ルガモン」
「なんだよ。おれは眠いんだ」
やる気のない声が返った。眠いときにちょっかいをだすと不機嫌になるので、ほうっておく。
「教授に質問! こっち……リアルワールドでもデジモンがしゃべってるんですけど!」
まず、基本的な質問をぶつけた。
「いちどマインドリンクをしたデジモンは、以降、いつでも言語によるコミュニケーションが可能になる」
龍泉寺が答えた。
マインドリンク済みのデジモンとは、非マインドリンク時であっても会話が可能になるのだ。
「てことは……DDLには、ほかにもしゃべるデジモンがいるんだ!」
さっき教授は「過去の例からも」と言っていた。
「もちろんそれは……企業秘密だ。〝D4〟」
龍泉寺は暗に認めた。
DDLはAE社の最先端研究所だ。D4区画ではスゴ腕のハッカーやクラッカー、強力なデジモンを抱えているのだろうか。
「で、仕事のことですけど」
本題に入る。
エイジが今日、龍泉寺のもとを訪れたのは仕事の中間報告のためだ。
武闘派クラックチーム・サンズオブケイオス(SoC)への潜入調査。
謎のリーダー、クラッカー・タルタロスに接触を図り「大規模な作戦行動」について探ること。そのためにエイジはSoCへの加入を試みた。
「――SoCの入隊テストに合格しました。面接官から合格メッセージが届いて」
エイジはスマホを見せた。
あのネクタイ鉢巻アイコンの面接官から、GriMMに合格通知のメッセージが届いている。
「ちなみにテストの内容は?」
「ウォールスラム9番街の調査です」
「あそこはクラッカーやデジ対ですら二の足を踏む危険地帯だね」
「マインドリンクのおかげで、ヨユーでした! ラッキーなことにルガモンが……昔、ウォールスラムで暮らしてたみたいで。9番街は、こいつのジモトだったんですよねー」
「ふむ」
「龍泉寺教授は知ってたんですか、そのこと」
エイジは気になってたずねた。
「彼はね……ルガモンは」龍泉寺は言葉を選んだ。「われわれDDLがウォールスラムで回収、保護したんだ」
「保護……?」
「詳しくは企業秘密だ」
「D4?」
「そう……ルガモンの記憶について気づいたことはあるかい?」
龍泉寺はエイジにたずねた。
「9番街に残っていた自分の臭いを嗅いだとき、少しだけ思いだしたみたいです。成熟期……ルガルモンになれたのも、進化したというよりは……こいつ、もともと成熟期で、それを思いだしたのかなぁって」
エイジの直感だったが。
「ふむ……あるべきチカラを取りもどしたということか」
龍泉寺は納得したようにうなずく。
「もっとも、ほかのことは覚えていなくて。でも、ウォールスラムのほかのデジモンたちは、ルガルモンのこと覚えていましたよ。〝九狼城の魔狼〟……だったかな」
ふたつ名がつくほどの、あたりのボス格のデジモンだったようだ。
「――こいつの俺様、王様な性格も、もとからのものだったのかなぁ……? おれの育成が間違ってたわけじゃなくて、よかったけど!」
「すでに気づいているだろうが、ルガモンは記憶野にエラーが認められる。人間でいえば記憶喪失だ」
あらためて龍泉寺が言った。
「はい」
「もしかすると、そのことで、これから苦しみ悩むようなことがあるかもしれない。そんなとき、エイジくん……きみが、ぜひルガモンのそばにいてあげてほしい」
――デジモンと心からむかいあってほしい。
龍泉寺が、ルガモンのことを気遣っていることが伝わった。
彼にとってもルガモンは、ただのAIプログラムではないのだろう。
「もちろん!」
エイジはソファのルガモンを見た。
デジタルワールドではエイジがホロライズして、リアルワールドでは、こうしてデジモンがホロライズする。
「――おれ、自分がデジタルワールドでホロライズしてみて、なんかルガモンの気持ちが少しだけわかった気がしました。デジモンの気持ちっていうか……」
うまく言えないのだが……。
「そうか。きみのような若いクラッカーに出会えて、私もよかった」
「…………! おれ、龍泉寺教授と出会って、ルガモンと出会って……いろんなことが動きだした気がするんだ! だから、おれはやっぱり、ルガモンといっしょにデジタルワールドで人生を変えたい!」
「人生……では、きみたちはパートナーということだね」
その龍泉寺の言葉が、エイジの心にしっくりきた。
「はい!」
ルガモンは、エイジにとって、たがいにデジタルワールドで生きていくためのパートナーデジモンだと。
それがエイジの、ルガモンへの率直な気持ちだ。
そして、できればルガモンにも自分のことをそう思ってもらいたい。
そうしたら、なんでもできるんじゃないか。デジタルワールドで成りあがって人生を変えることだって。
「ああ、そうだ……成熟期に進化したのでインセンティブの支払いだね」
「追加報酬! やったぁ!」
エイジにとっては破格のギャラだ。
10万、50万というお金であっても、時給いくらで働いていたら貯められない。毎月の家賃、カードの支払いに困ることも、しばらくはないはずだ。これは、とんでもなく安心感があった。
(今夜はお寿司だ)
もうすでに、デジタルワールドでの小さな成功が、エイジのリアルの人生を変えつつあった。
この安心感があればこそ、ここからリスクをとって勝負をかけることができる。
「エイジくん。きみは引き続きSoCの調査を」
「正式にSoCのメンバーになりました。さっそく幹部からコンタクトがあったので、これから出向きます」
「仕事が早いね、きみは」
「マインドリンクは効果てきめんなんですよ! 一流の名刺代わりで」
マインドリンカーというだけで相手からリスペクトしてもらえる。
エイジが腕に巻いたデジモンリンカーは、どんな高級時計よりもすばらしいステータスなのだ。
「ちなみにSoCの、だれと会うのかね」
「ええと……」
エイジはスマホでメッセージを確かめた。
――Marvin
「クラッカー……マーヴィン、かな。まだメッセージのやりとりだけですけど」
「〝ソングスミス〟マーヴィンか! 大物だな」
龍泉寺がそんなふうにだれかに興味をしめすのは、珍しい。
「有名です?」
「曲を奏でるようにコードを組むクラッカーだよ。きみたちがいつも使っている、その……GriMMの主要な開発者のひとりだ」
といえば世界屈指のエンジニアであるということ。
SNSと金融決済ツールを兼ねたGriMMは、高度なセキュリティによってサービスが保全されている。これは、とてつもない信頼性があるということだ。
一方で、まともな企業であれば仕事でGriMMは使えない。開発、運営しているのが有志のクラッカーというのでは……。しかし実際には、公的機関や軍などでGriMMをお手軽に使うケースが後を絶たず、安全保障上の問題になっていた。
「大物……! なら、マーヴィンの部屋のドアひとつむこうには、リーダー・タルタロスがいるかも」
「エイジくん、きみの仕事はスパイだ。SoCの内部にとどまり、きみの正体を知られることなく、なるべく長く活動してほしい」
「はい!」
「では……SoCの幹部と接触する前に、あらためて大切なことを伝えよう。きみの生命にかかわる重要なことだ」
龍泉寺はモニタにファイルをひらいた。
――『禁D4 第■■■回ML実験 ■■■■年■■月■■日 於DDL』
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo