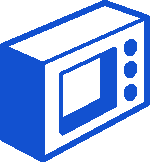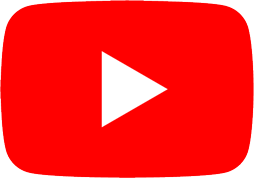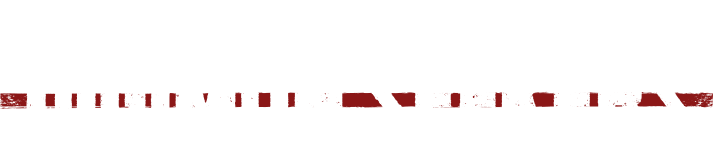-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER1
Eiji:Wolf of ninth avenue
Chap.1-4
龍泉寺がいった。「デジモンは生きている」と。
「――ほんとうにデジモン生きていたら、たのしいですよね! いまもデジモンを、デジタルペットみたいに飼う趣味のマニアはいるし、龍泉寺教授みたいなコレクターもいるけど。おれみたいなクラッカーにとってデジモンは……便利なAIツールかな」
エイジにとってデジモンは大切な、仕事道具だ。
エイジは、いまはティラノモンを愛用している。デジタルワールドでは比較的よく捕獲されるデジモンで、GriMMでたくさんの個体が取引されていた。
「ふむ」
「いつ、どこにできるんです? その『デジモンランド』」
「永遠にお蔵入りというやつだ」
龍泉寺は残念そうに息をもらした。
「あらら」
「現実的にはむずかしい。だからデジタルワールドは〝人類の秘密〟のままなんだ」
龍泉寺の言葉に、エイジの脳裏を、さっき見せられた航空機の墜落映像がよぎった。
「デジモンを犯罪につかうやつがいますからね。同業者……たちのわるいクラッカーだけど」
クラッカーはおおむねグレーゾーンの存在だが、そのなかでも白黒はある。
白にちかいグレーと、まっ黒にちかいグレー。
話してみるといいやつらとガチでヤバいやつら、犯罪者、全人類の敵レベルのやつまで。
とにかく――
昨今、あちらこちらで頻発しているネットワーク障害、不正アクセスによる情報窃盗、サイバーテロ。そこに実は、すくなからずAIツールとしてのデジモンが関係している。
あの映像のように、テロリストが使用したデジモンが、実際に飛行機を墜としたとされる事件もあった。
そのことは、もちろんおおやけにはなっていない。
デジモンとデジタルワールドのことは、一般には知られていなかった。全世界の首脳たちと国際機関が、その存在自体を隠蔽――かくしてきたからだ。
いずれにしても、もしテーマパークのキャラクターが犯罪者の道具としてサイバーテロをおこした……なんてことになれば、不祥事がすぎるだろう。
「デジタルワールドとデジモンのことを世間におおっぴらにするということは、デジモン犯罪について世界に公表することにつながる。どうなると思う?」
「パニック!」
「まさに、だ」
デジモンは異世界からの侵略者、とか、不安をあおるのが仕事のマスコミがさわぎだすだろう。
わかりやすく短絡的に、デジタルワールドとデジモンは悪、となりかねない。
「未だ人類の大半はデジタルワールドを知らない。知ってはいても理解はしていない」
龍泉寺は天才らしく、エイジにはむずかしいことを口にした。
「…………」
「まさかネットワークのむこうに、現実世界とはべつの異世界があるなんてことは……デジモンという命が生きているということは」
知ってはいても理解はしていない。
「龍泉寺教授……」
それがクラッカー――デジタルワールドで、デジモンをつかって仕事をする自分にむけた言葉でもあることを、エイジは感じた。
デジモンは生きている。
「クラッカー・ファング……エイジくん、知りたくはないか? リアルワールドとデジタルワールド、ふたつの世界の真実を。セカイの裏側を見てみたくはないかね」
「そりゃ……見てみたい!」
エイジは興奮した。
「――だって、おれは知らないから! おれにとってデジタルワールドは……そのデジモンドックのモノクロ画面の情報、それがすべてだ。でも教授、あなたが見てる……見てきたセカイはきっと、ちがうんでしょう? そうだ、さっき映像で見た景色――」
ネットワークの海とリアルワールド、そしてデジタルワールド。
ノイズのむこうに垣間見えた、あのセカイは……。
「きみに見せた映像が、なぜ〝D4〟……わが社の最高機密なのか。人類の秘密とされているのか、わかるかね?」
「それは」エイジはひらめく。「あの映像が本物だからか!?」
フィクションのプロモーションビデオではなく、デジタルワールドを観測した映像だったから……?
「そう……あの景色は、観測データに基づいてAIが生成した真のデジタルワールドの想像図だ。そしてデジモンは、デジタルワールドでほんとうに生きている。地球外生命体は、外宇宙ではなくデジタルネットワーク上にいたというわけだ」
龍泉寺は、まっすぐな目でエイジを見る。
彼がいっていることは、たとえや、ものごとのとらえかたといった話ではなかった。
「デジモンは生きている……!」
エイジはホロライズしたモドキベタモンを見た。
生きている。
であれば、これまでAIツールとしてあつかってきたティラノモンたちも……? ほかの、すべてのデジモンたちも?
「デジタルワールドのありさま、デジモンのありさまを、この目で、じかに見ること。仮想モニタと観測データではない、人間の五感で直接デジタルワールドを、とらえること。
リアルワールドとデジタルワールドの〝軛(くびき)〟をこえる。
ありのままに。それこそ私が……この龍泉寺智則が、人生をかけてとりくんできた研究だ。ゆえに私のすべてが〝D4〟なんだ」
モドキベタモンのデータ移行が完了した。
龍泉寺はエイジの納品用デジモンドックを機器からはずすと、指でつまんでながめる。
「…………。あ、ども」
エイジは手をだした。
ポイッ
龍泉寺はデジモンドックをほうってしまった。
「えええええ?」
びっくりする間もなく、エイジはヘッドスライディングするいきおいで、デジモンドックがゴミ箱に落ちる寸前でキャッチした。
「なにするの、教授!」
いきおいあまってゴミ箱に顔面ダイブしてしまった。
エイジのドックはパーツを組んだ自作品だ。ジャンクとはいえ、お金がかかっている。
「それ、メモリ領域にエラーがあったよ」
「マジですか!?」
龍泉寺はデジモンコレクターだ。データのコンディションには人一倍、気をつかうのだ。
「旧式はつかわないほうがいい。私からの仕事のときは、とくにだ……あやうくモドキベタモンのデータが壊れるところだった」
「にしても捨てることないでしょ……あのね教授、フリーのクラッカーのふところ事情は、大企業とはちがうんですよ? なんもかんも自腹、領収書とかきれないし、ここにあるようなハイスペな機材を好きなだけつかいつぶせるわけじゃないんだから」
「ふむ」
「……はい?」
エイジはとまどった。
龍泉寺は、ちょっと独特な間のある話しかたをする。
なんといっても日本がほこる天才科学者だ。一風、変わり者であるくらいはゆるされるのだろうが。
「それはすまなかった。ああ……だがちょうどいい。腕だして」
「?」
なにがちょうどいいのかわからなかったが、いわれたとおりにする。
龍泉寺はエイジの左手首になにかをまいてつけた。
エイジは……息をのむ。
「…………ッ!」
こんな気もちになったのは、いつ以来だろう……。
子供のころ、あたらしいゲーム機を親に買ってもらったとき? はじめてスマホを買ってもらったとき?
いいや、その何倍も……!
この身につけただけで世界がひろがっていく予感は。
「これを、きみにあげよう」
腕時計型のガジェットだった。
「アバディンエレクトロニクス製……最新型デジモンドック? しかもスマートウォッチタイプ!」
エイジはジャンプして3回転半したい気分だった。
もともとAE社の製品はデジモンドックに改造しやすく、クラッカーのあいだで評価がたかい。しかも、これは純正品。デジモンがらみということで企業秘密に属しているブツだ。

――デジモンリンカー
「私が設計にかかわっている製品の、試作品だ」
「龍泉寺教授……あんた、知ってたけどすげぇ!」
エイジの腕で、腕時計型デジモンドックが自動セットアップをはじめる。
「私はデジモンドック部門の技術統括責任者でもあるのでね。それには生体情報……バイタルセンサーがついているので、いま登録したきみにしかつかえない」
「おお! おれ専用!」
「医療機器クラスのセンサーだから。脈拍、血圧、呼吸、体温、そういうのぜんぶ記録してるから。うちのライフサポートで24時間、安心の医療サポート体制つき」
「健康になっちまうじゃん!」
エイジはノリでかえした。
「ホロライズ機能もサポートしている。本来、デジモンのホロライズはこのDDLのほか、かぎられた施設内でしか許可されていないのだが……特例だ」
とにかく特別、特別、特別あつかい。
「でも試作品って……いいんですか? なんか裏があるんじゃ」
「安心したまえ。これは私個人から、きみへのプレゼントだよ」
「マジすげぇ!」
「さて、そこでだ」
「ほら、やっぱ裏あるじゃん! 教授の性格だんだんわかってきたんだ、おれ」
まぜっかえしたが、エイジはこのスマートウォッチ型デジモンドックを手ばなすつもりなどない。
ほしい。
デジモンリンカーは、誇張ぬきでエイジの自作ドックとはケタちがい、2ケタちがう性能があるはず。
「そこでクラッカー・ファングを見こんで、つぎの仕事をたのみたい」
「やります」
「即答だね。実にいい、きみのそういうところが好きだよ」
龍泉寺はエイジの腕をとると、デジモンリンカー側面にあるスイッチを押した。
画面が、ほのかにかがやく。
ふしぎな炎が、時計の画面からゆらめきたったように見えた。
――ルガモン 成長期 魔獣型 ウィルス種
ちいさなカラー画面には見たことのないデジモンが映っていた。
エイジは目をほそめる。
「わんこ……犬?」

龍泉寺教授からあらたな依頼をうけたエイジは、ひとりでゲートをくぐって1Fの受付ホールにもどった。
「リアルワールドとデジタルワールドの軛をこえる……か」
ホールの中央では、例の三つ巴のオブジェがホロライズされている。
「あ、おつかれさまです!」
受付で、初音のほうから話しかけてきた。
「パスは、ここにかえせばいいの?」
「こちらにご返却ください。ありがとうございます」
エイジはパスをわたした。
その腕にまかれていたものに、初音が気づく。
「…………」
「あ、これ? 龍泉寺教授にもらったんだ。……知ってる? デジモンドック」
エイジは新品のスマートウォッチ型ガジェットを初音に見せびらかした。
初音はキョロキョロとまわりを見てから、ささやきかえした。
「機密ですよね、最新型」
受付という立場だからかどうなのか、なかなかの情報通らしい。
「試作品のテストなんだけどねー」
「すごい。あの龍泉寺教授から、じきじきにテストを依頼されるなんて……永住さん、ものすごく信頼されてるんですねっ」
お世辞ではなく、初音は心からおどろいていた。
「んー……そうなのかな。逆に、そうなの?」
「ぜったいですよ……! 龍泉寺教授はああ見えてとても――」初音はさらに小声になった。「気むずかしいところがあるんですから」
「あー、独特かな」
エイジはつい、ふきだしてしまった。
初音の態度が最初とはぜんぜんちがったからだ。でも、これはこれでわるくない。
「じゃ、また」
「あ、永住さん」
「エイジでいいよ」
「私も……初音ちゃんでも初音っちでもいいですよ! それで……エイジさんの入場記録なのですけど。ご職業のところが、まだ空欄だったので! さしつかえなければ教えていただけますか……?」
初音は、なにかを勝手に期待して、そわそわしていた。
「ご職業?」
エイジはちょっと考えた。
フリーター……は職業ではない。定職がないというだけだ。
「――永住瑛士、職業はクラッカー」
「えー」
初音は今日イチ微妙な反応をかえしたのだった。
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo