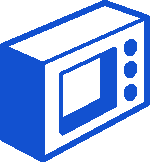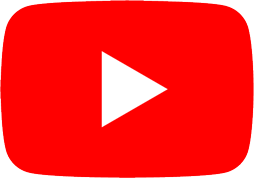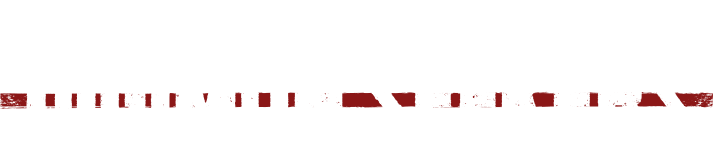-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER1
Eiji:Wolf of ninth avenue
Chap.1-2
東京電脳大学は、科学技術と国の未来をになう理系学生を優遇・サポートする政府の目玉政策として設立された。
歴史こそ浅いが、情報工学の分野においてトップクラスの研究と実績をほこる。多国籍都市・東京のあらたな中心となった電臨区という立地。グローバル企業、いわゆるビッグテックへの就職につよいという評価もあって、ますます受験生の人気はたかい。
その電脳大・電臨キャンパスに隣接して、もうひとつの施設があった。
アバディンエレクトロニクス(Abadin Electronics Corp. AE社)。
電子端末、ネットワーク機器、ファブレス半導体などを手がけるトップ企業だ。
アバディンエレクトロニクス・電臨区デジタルラボ――通称DDLは、AE社の研究開発拠点だった。


DDLの1Fロビーは、エイジが想像していたよりもシンプルだった。
受付、ありふれた待合のベンチ。
壁面の大型ディスプレイではAE社の宣伝をしているわけでもなく……大草原、密林、極海、大山脈、紅葉の急流、地底と洞窟……それら四季折々の自然がおりなす環境映像が、ただ、ながされていた。
「デジタルラボは研究施設だしな……AE社の本社はよそだし」
なだらかな曲面で構成されたラボの外壁は緑化されて、会社のロゴ、それとわかる看板などもない。通行人は、となりの電脳大の建物だと思うかもしれない。
エイジはガラスに映った自分を見た。
いつものラフな服装だ。DDLの勤務はカジュアルウェア可ではあるようなのだが。
ここで働いているのは、えりすぐりの頭脳をもったエリートばかりのはず。高卒フリーターは場ちがいだ。
でもエイジは気おくれせず受付に歩く。
そう、仕事だから。
「こんちわー」
エイジは愛想をふりまいた。受付の彼女に。
「はい?」
なに、この挙動不審なワカゾーくんは……? といった感じの彼女の目線がかえった。
四角いリュックを背負っていないので、フードデリバリーじゃないのはわかるはずだ。
ああ、そうか……たぶん、まちがえてラボに入ってきてしまう大学生やら通行人が、たまにいるのだ。そういう手合いだと思われたのだろう。
「約束があるんだけど。このタブレットに打てばいいのかな?」
研究施設ともなると企業秘密をかかえている。
むこうのゲートには屈強なガードマンが数人つめていた。ここがアメリカだったら拳銃くらい所持していそうな、ものものしい雰囲気だ。
「はい……でしたら……」
とまどう声もかわいい。
襟元にかけてくびれたボリュームのあるショートヘア。研究所らしく地味めな事務員スタイルだが、小顔で、首と肩がほそくて、とにかくいるだけでモテるんだろうなぁという感じだ。
「――氏名のところは本名? おれ、仕事ではべつの名前をつかってるんだけど」
「失礼ですが芸能界とか作家の方ですか」
「いーえ」
芸名やらペンネームではない。エイジは、大多数のクラッカーがそうであるように、仕事では通り名のクラッカーネームをつかっている。
「さしつかえなければご本名で」
「永住瑛士……と。電話番号、約束の時間……用件は商談とかでいいの? 初音ちゃん」
エイジは相手の名札を見ていった。
「いきなり、ちゃんづけはやめてください」
「じゃあ、初音っち」
「…………!」受付の初音は、こめかみのあたりをピクピクさせた。「ご商談でしたら、こちらに御社の……」
「まだ会社にはしてないんだよねー」
「はぁ」
「えーっと、おれの職業は……そういやあの人の部署ってなんだっけ? ああ、もう、めんどうだな」
エイジはスマホを手にした。
――龍泉寺智則(教授)
アドレスをタップして「つきましたよ」のメッセージを送ると、ロビーでまつことにした。
ほかに来客は数人。受付でゲストパスをわたされている。みな営業のビジネスマンというよりは、それこそ電脳大にいそうなアカデミックな空気をまとっていた。
(…………)
エイジはふと、ロビー中央のオブジェに目をやった。
3つの球体が宙にうかんでいた。
球体には、それぞれに特徴的なマークが刻まれている。
三つ巴――とでもいうのか。それらは、たがいに重なりあいながら回転していた。さながら宇宙空間で、たがいに重力でひかれあう3つの球状星団。
(というか、こんなのさっきまであったっけ……?)
ちかづいてみて、エイジはおどろいた。
「これ立体映像……〝ホロライズ〟か!」
「――やぁ〝ファング〟!」
ゲートのむこうから、クラッカーネームでよびかける声が飛んだ。
と同時に、三つ巴のオブジェはくずれながら跡形もなく消える。
エイジはふりかえった。
身長は170センチほど。彫りの深いロマンスグレイで、ちょっと白人っぽい雰囲気もあった。年齢は60代のはずだが、足どりも姿勢もよく、ずっと若く見えた。
その存在感は、彼本人よりも、まわりの反応を見たほうがわかりやすい。ロビーにいた全員が、思いがけずあらわれた彼に注目したのだ。
「ども、龍泉寺……教授!」
アバディンエレクトロニクスの共同創業者のひとり。
大富豪だ。時価総額1000億ドルをこえるAE社の株式を、未だに20パーセントあまり保有している。
教授、というのは、彼は大学教授でもあったから。
業界では知られた龍泉寺研究室のボスにして現在は電脳大名誉教授。かつて大学発のベンチャーとして起業した彼の会社を、最高幹部のひとりとして10年、20年でここまでの世界的企業にそだてあげた。
「クラッカー・ファングとこうして会うのははじめてだが、そんな気がしないね」
雲の上の人、というのだろう。
ふつうに考えれば、龍泉寺はエイジが気安く接することができる立場の人ではない。
「いつもボイチャで話してますからね。あ、永住瑛士です」
エイジはあらためて自己紹介した。
「さっそくだがファング――エイジくん、行こうか。すまないね、いろいろめんどうで。ああ……きみ、彼にゲストパスを」
龍泉寺が受付にいった
あやしいワカゾーくんが、日本AE社の事実上のボスを気安くよびつけたものだから、受付の初音のほうがあわあわと挙動不審になってしまった。
「はい! すぐに……」
「〝D4〟に行くので共同研究者パスをたのむ」
「えっ」
「取締役会の決裁はとった。今日の午前中にね」
「はい……あ、たしかに!」
端末をたたいて確認すると、初音は2度びっくりしながらパスを発給したのだった。

発給された特別なパスをかざして、最敬礼の警備員たちを横目に探知ゲートをくぐる。
それだけでエイジは、なんだかすこし大人になった気がした。
廊下を歩いていると、すれちがう社員、研究者たちが龍泉寺にあいさつをする。エイジはそのうしろにひっついてキョロキョロしながらペコペコしかえした。
それはそれで、なんだか、すごくいいのだ。
「龍泉寺教授って、なんで〝教授〟なんです? 社長とか副社長とか、会長とかじゃなくて」
「大学教授が性にあっているんだろうね」
研究者気質ということだ。AE社の経営は、かつての部下たちにまかせているという。
エイジとしても、大企業の経営者様とはどう接すればいいのかわからないが、大学の先生というなら、いくらかは話しやすい。
「オフィスに行くまえに、よりたいところがある。ぜひ、きみに見てもらいたくてね」
「なんだろう、たのしみだな!」
「こっちだ」
エレベーターで階を移動すると、また警備員がいる厳重なゲートがあった。
ロビーにあった空港みたいな探知ゲートではない。隔壁だ。DDLの建物内で、ここからは完全に独立しているようだ。
――D4区画
「ここからはアバディンエレクトロニクスの最高機密となる。わが社の今後をになう、核心となる研究がおこなわれている」
龍泉寺が説明した。
AE社の最先端研究所であるDDL、その核心がD4区画。
エイジは、スマホと所持品を警備員にあずけさせられた。さらに厳重なボディチェックを受ける。
「…………」
「なにかね?」
さきに隔壁ゲートをくぐった龍泉寺が、エイジをふりかえった。
「えーと、心の準備が」
「なぁに、ちょっとした〝体験〟をしてもらうだけだ。アトラクションはきらいかな?」
「え? たのしいやつ?」
「うんうん……遺伝子操作で恐竜を復活させたり、ゾンビウイルスの研究をしてるわけじゃないが」
「そっちの展開もおもしろいですけど」
龍泉寺のジョークでリラックスすると、エイジはD4ゲートをくぐった
そこには――
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo