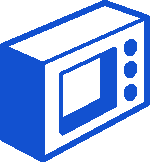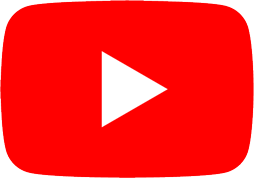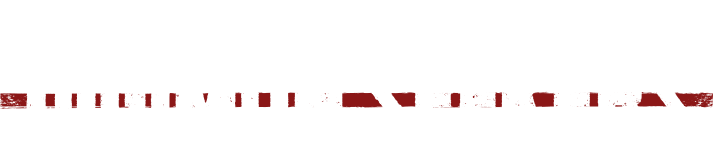-
アニメポータル公式
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
Anime Potal
-
デジモン公式チャンネル
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
Digimon Official Channel
-
デジモンカードゲーム公式チャンネル
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
Digimon Card Game Official Channel
- JP
- EN
- 簡中
CHAPTER1
Eiji:Wolf of ninth avenue
Chap.1-11
「――この声、ルガモンなんだろ? できたら説明……ご説明ねがえないでしょうか」
エイジはなぜだか敬語になってたずねた。
「説明……? なんのだ」
「一から十まで理解不能です」
ここは、どこだ。
なんで、デジモンがしゃべっている。
エイジは、どうなってしまったのだ。
自宅のロフトにいたはずなのに……!
「ナガスミ・エイジ……おまえ、リューセンジの説明を聞いていなかったのか」
「え? 龍泉寺?」
ルガモンが教授をよびすてにしたので、エイジは面食らった。
「〝マインドリンク〟の説明だよ」
――SoCへの潜入にあたって、きみのデジモンリンカーの機能を限定解除した。
AE社とDDLの最高機密、D4の研究成果。
クラッカーとしてのスキルを一気にアップする方法だともいっていた。
「ええと……超一流のクラッカーになれる機能……だよね」
「やれやれ」
「だって教授の説明、ときどき、むずかしくてさぁ」
テキトーに相槌を打っていたのがバレてしまって、エイジはちょっと気まずい。
ルガモンが歩きだす。
「――あ、そこ、割れたガラスがあるから気をつけ……」
いいかけたエイジは、気づいた。
ビルの窓ガラスに、ゆらめく炎に照らされたデジモンの姿が映っていた。
ルガモンだ。
「…………」窓ガラスに映っているのは、いくら目をこらしてもルガモンだけだ。「おれが……いない?」
これは……。
エイジは、ルガモンが見ている世界を見ている……?
ダッ
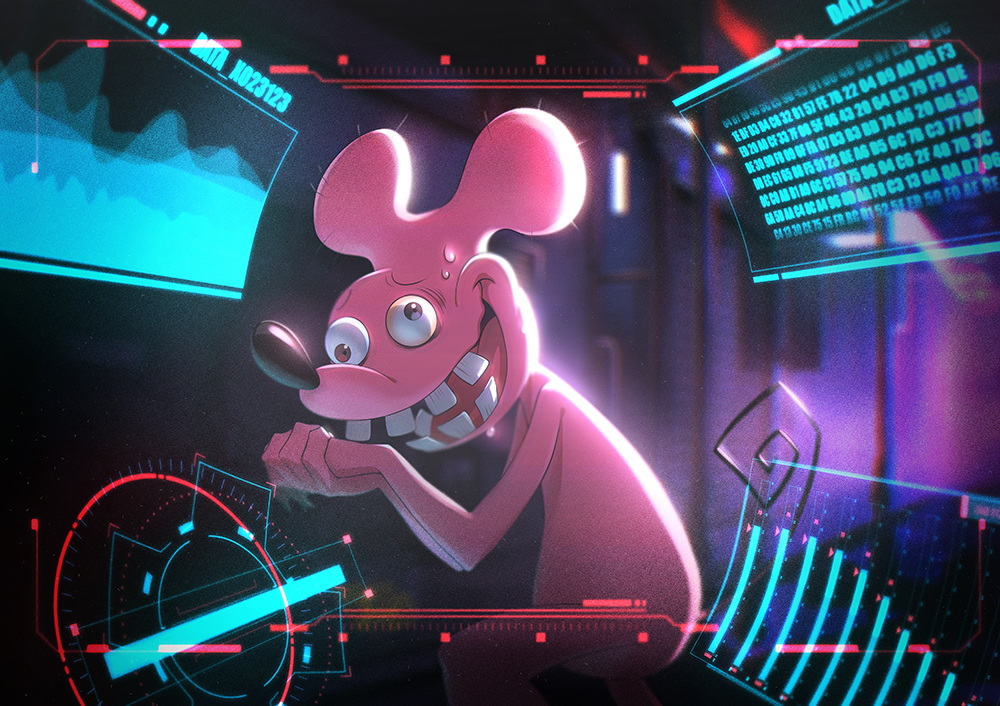
そこに、もうひとりのネズミがかけよってきた。
「ダンナ! おみそれしました、まさか九狼城の親分さんとは……! 手前はチューモン、つまらねぇネズミのデジモンです!」
なりゆきでたすけられたチューモンがあいさつをした。
「…………」
「失礼ですが、どこぞにおでかけだったんで……? ここのところ親分さんの名前を、とんと聞かなかったものですから。うわさじゃ、暗殺者にデジタマにかえされたとか、人間に捕まったとか……」
チューモンがさぐりを入れてきた。
「だれにことわって、おれに話しかけてんだ」
ルガモンはうなった。
「チュー! すいません!」
「おれをタマにかえす暗殺者や、首輪をつけられる人間がいるとでも……?」
「し、し、し、失礼しましたー!」
チューモンはビビりまくっている。
ルガモンは息をつくと、すっと頭をあげた。
「そう、思いだしてきた……“ダストキングダム”――おまえらチューモンは5番街のゴミための支配者・スカモン大王の手下だったな」
「へい!」
「これからは、おれが目をかけてやる。おまえは、さっきのぬいぐるみとちがってうまそうだしな」
ルガモンはチューモンを鼻先でかいで、ぺろっとなめた。
(うげっ)
そのネズミの臭いと舌ざわりが、なぜかエイジにもわかったので、ショックで混乱する。
「ひぃいいいい! このチューモン、お役に立ちます!」
「〝九狼城の魔狼〟……か」
なつかしいひびきだ。ルガモンがつぶやいた。
「――おい、チューモン」
「へい!」
「おれは……人間に捕まったことになっているのか?」
「うわさです! 親分がいなくなった9番街は、いまじゃすっかり不景気……さびれちまって」
「留守のあいだに、ウォールスラムもずいぶんかわったらしいな……こづかいだ、とっとけ」
ルガモンはエサを投げた。
「これは……リアルワールド製のエサ肉! さすが親分さん、いいもの食ってる~! それじゃ!」
エサ肉とチーズをかきあつめると、チューモンは、もう二度と会いたくないといった感じで逃げていった。
「あの……お話、おわりました?」
エイジはおそるおそるルガモンに話しかけた。
ルガモンは、なぜか、ため息をついた。
「説明、だったか」
「ぜひ!」
「こういうとき人間は、なんていうんだったか……『百聞は一見にしかず』? 『論より証拠』?」
「え……うぉっ!」
いきなりだった。
ルガモンが割れた窓から身を投げた。
エイジにとってははじめての、自由落下の体感。
3~4階くらいの高さからなんなく着地すると、ふりあおぐ。
そこは、ビルの谷間だ。
暗い摩天楼――きらびやかさとは無縁の、ひとけのない夜明けまえの副都心あたりを思わせた。窓ガラスには、まったく明かりがついていない。
あたりでいちばんたかいビルにとりつくと、ルガモンは駆けあがった。
垂直の壁を。
ツメをくいこませて疾走する。

肌に風をうけて。
ルガモンの目を、耳を、鼻を、舌を、肌を、すべての五感をエイジも共有し、感じていた。
「そうか……龍泉寺教授の研究成果! これがD4の最高機密テクノロジー!」
現実世界リアルワールドとは、なりたちがことなるデジタルワールドを、人間が直接、知覚することはできない。
たとえば計器とソナーをたよりにする潜水艦、宇宙空間を旅する探査機のように。観測されたデータによって、間接的にしか、まわりの状況を認識できないのだ。
なんとかして人間の五感でデジタルワールドにふれることはできないか……?
その可能性を探究した末、デジタル生命体であるデジモンの〝デジコア〟とよばれる部位に人間の〝精神データ〟を転送、〝意識〟を設定することで、かぎりなく実感にちかい知覚をえられるとわかった。
「マインドリンクは人間の精神をデジタルデータ化、おれたちデジモンのデジコア領域に、その人間の意識を転送するテクノロジーだ」
話しながら、ルガモンは息ひとつきらさず高層ビルを駆けあがった。
デジコアは、デジモンの核となるデータ領域だ。
生命としての核であり、そのデジモンが、その個体であることをしめす領域――自我、いわばデジモンの魂。
「うん! 教授、そんなこといってた!」
腑に落ちてしまえば、とまどいよりも興味がまさった。
ちいさなモノクロ液晶画面じゃない。
デジタルワールドのありさま、デジモンのありさまを、この目で、じかに見る。仮想モニタと観測データではない、人間の五感で直接デジタルワールドを、とらえる。
龍泉寺は、その技術を、すでに完成させていたのだ。
これが答えだ。――〝マインドリンク〟
「おれ、デジモンになってるみたいだ! マインドリンク……これが超一流が見ている世界なのか!」
エイジは興奮した。
「はじめてのマインドリンクだ。おまえが混乱したのは仕方がない。そのうちなれる」
「うん、なれてきた! でも、いつ、おれの精神データとかデジタルデータ化したんだろう?」
「デジモンリンカーで、おまえの生体情報、脳波、意識レベルを24時間サンプリングしていた」
「マジで! おれの個人情報ダダ漏れじゃん!」
「なにをいまさら……そのためのデジモンリンカーだ。なにしろ人間の精神をデジタルデータ化しようとすれば膨大なデータ量になる」
「龍泉寺教授、すげー……すごすぎる」
「…………。あと、質問は? デジコアのなかで、いちいちぎゃーぎゃーさわがれるのはウゼェ」
「おれ、なんで話せるんだ? デジモンと!」
「ばかばかしい質問だ。おれたちデジモンは生きているからだ。これまでも、これからもずっと」
デジモンは生きている。
ルガモンもティラノモンも、ほかのデジモンたちも。
「そっか……デジモンは、ずっと、おれに話しかけていたんだな……」
「おまえがおれたちデジモンに、ちょっとばかりちかづいてきたってだけだろ」
高層ビルをかけあがったルガモンは、ついに屋上に立った。
そこにあった景色は――
キャラクターデザイン・挿絵イラストレーター:malo